検索結果
-

PROGRAM/放送作品
タイムマシン
未来を創るのは「夢+○○」?…恋人を救う為、80万年の時を超える!超世代SFアドベンチャー!
H・G・ウェルズの同名原作を、曾孫でアニメーション映画を多く手がけるサイモン・ウェルズが監督となり実写映画化したSFアドベンチャー。1959年に続く再映画化である。主演は『メメント』のガイ・ピアース。
-

COLUMN/コラム2016.12.17
ゾンビ映画ファンだけでなく、ゾンビ嫌いな人にも観て欲しい、2人の愛を見せつけられる秀作ドラマ『ゾンビ・リミット』
ちょうど1981年~1985年は、リターンドと名づけられた未知のウィルスが発見され、多数の死者を出した第1次流行期にあたる。そのウィルスの感染者はリターンドと呼ばれた。感染者が出血した場合、他者は決して血に触れてはならないし、感染者をそのまま放置すれば、数日後には意識を喪失し、生肉と血に飢えたゾンビのように凶暴性を発揮する。 これは現代史において人類最大の悲劇となり、現在まで世界中の犠牲者は1億人以上とされる。第1次流行期から治療を研究しはじめて10年後、リターンド(感染者)の髄液から採取した“リターンドたんぱく質”により大きな希望がもたらされた。そして第2次流行期以後は、多くの人を救うことができた。 でも全てのリターンドを完治できるわけではなく、感染後、36時間以内に薬“リターンドたんぱく質”を注射し、効果があらわれた者だけしか助からないし、助かった者も一生、薬をうち続けなければならない。国はリターンドに薬を配給し、患者を管理していた。 一方、リターンドへの反発は徐々に大きくなり、反リターンド派のみならず一般市民による差別やデモが相次ぎ、各地でリターンドが襲撃される暴行死傷事件が起きていた。そのため、リターンドは密かに暮らし、周囲にカミングアウトすることはなかった。 ゾンビのような凶暴化した人間を生み出す新種のウィルスに対する反応を、多少のシミュレーション風に描いたものでは、『28日後…』(02)の続編『28週後…』(07)が思いだされる。感染者の恐怖とそれに対する社会(世界)の対応が描写されていたが、見せ場のメインは、ゾンビのような感染者が人間に襲いかかる光景だった。 でも『ゾンビ・リミット』では、未知のウィルスに感染したリターンドが徐々に増殖してゆき、それに対する社会と人間たちの様々な反応を描いたドラマであって、ゾンビのように凶暴化したリターンドが人間に襲いかかる描写はほんのわずかしかない。だから、そのテの凄惨な残酷描写を期待するファンにとっては、最初は肩すかしを喰らった感があるかもしれないが、それでも徐々に見応えある作品世界に没入してゆくハズ。 ゾンビ映画をリスペクトしつつも、ゾンビ映画の見どころの一つ、感染者の人間襲撃場面を極力排している。でも筆者は、それでも本作が大好き。愛すべき作品である。しかしこの邦題は、あまり好きじゃない。原題は“THE RETURNED”で、未知のウィルス名、およびその感染者を指すが、RETURNEDだけなら「戻ってきた」という意味がある。薬“リターンドたんぱく質”の効果によって、ゾンビ化から戻ってくるという意味もあるためか、邦題は劇場公開やレンタル・ビデオ市場を考慮し、分かりやすいゾンビの語を使用し、ゾンビ化への限界点を意味するだろう『ゾンビ・リミット』と名づけたのかもしれない。 主人公は、ミュージシャンでギターの講師もするリターンドのアレックスと、その恋人のリターンド治療医師のケイト。 6年前のある日、アレックスがショップで倒れている中年男性を助けようとしたところ、実は彼がリターンドとは分からず、指を咬まれてしまう。アレックスを診察したのがケイトで、2人はリターンドと担当医師という関係を超えて愛を育むことになる。 ケイトは、日々リターンド患者を診察し、彼らに対して慌てさせないよう優しく接する。感染した幼い子供をもつ両親が、「“リターンドたんぱく質”の在庫はあとわずかという噂が流れているが……」と質問されると、ケイトは「根も葉もないデマよ」とキッパリ。国はリターンドをできる限り増やさないよう、感染者に“リターンドたんぱく質”を配給し続けているのだから、必然的にそれを採取できる感染者は減少してくる。それを早くから察知していた国側は、“リターンドたんぱく質”の代わりになる、人工開発された“合成たんぱく質”の研究開発に着手するが、未だ完成にいたっていない。 ケイトはその事実を知っていても、優しい女医を演じて嘘をつき続け、しかも自分の勤務病院の薬品管理部の女性を通じて、アレックスのために密かに“リターンドたんぱく質”を高額で横流ししてもらっている。ケイトはエゴにはしってしまい、リターンドの治療医師にあるまじき行為を取っていた。アレックスも、彼女の行為をありがたいと感じながらも反道徳的な行為に対して何も言わない。2人の部屋の冷蔵庫には、手に入れた“リターンドたんぱく質”のアンプルがたくさん隠してある。 そんな2人の姿を見ていると人間の本性を感じ取ると同時に、この世界観に説得力が増してくる。ケイトは、アレックスさえ今のままでいてくれれば、他の感染者=リターンドがどうなってもいいと考えているわけじゃない。ケイトがまだ子供だった頃、両親がリターンドとなり、哀しい出来事を体験した……だからこそ彼女は、リターンドの治療医師になったと推測できるし、かつて愛する者を救えなかった後悔が、アレックスのために横流しをさせたと理解できる。 しかも、ケイトのリターンドに対する気持ちが、前半のこんな場面で力強く迫ってきた。ある日ケイトが勤務する病院に、黒い目だし帽を被った反リターンドの過激派が銃を持って襲撃した! 彼らはケイトに銃をつきつけ、「いかれているな、ゾンビのお世話か?」と揶揄した。するとケイトは、「彼らは、リターンドよ」と気丈に言い返した。怒った過激派は、更に「(彼らを)ゾンビと言え」と銃を向けていきがるが、彼女は決して「ゾンビ」とは言わなかった。 だからケイトは、たとえ社会や民衆がリターンドをゾンビと表現しようとも、自身の中ではあくまでリターンドという思いが強い。このケイトの思いを感じ取れる人なら、邦題の『ゾンビ・リミット』には少々抵抗があるハズだ。 そして、ケイトの病院に入院中だったリターンド患者は、過激派によって全員射殺され、リターンド=感染者の名簿を奪われてしまう。 過激派によるリターンド患者殺害の衝撃は、2016年7月に起きた「相模原障害者施設殺傷事件」の加害者のように傲慢だが、それは彼らだけではなかった。感染者=リターンドは社会の弱者でありマイノリティで、“リターンドたんばく質”の在庫薄が明らかにされると、リターンドの社会の風当たりは一層強くなっていく。 反リターンド派によって、“リターンドたんぱく質”配布所や病院が続けざまに襲撃され、しまいには病院そのものが軍の統治下に置かれた。そして国側がついに発令。「リターンドは、3日以内に監視センターに出頭しなければ逮捕する」と。大型バスに乗り込むリターンドたちの姿は、まるで第二次大戦でユダヤ人らがナチの強制収容所に運ばれる様とダブッてくる。 筆者も彼らをゾンビとは言いたくない……リターンド患者が増えてゆく世界を、リアル・シチュエーション風に描きつつ、アレックスとケイトの2人の愛と葛藤のドラマが展開する(それについての詳細は、ここでは書かないでおきます)。どうか本作を観て欲しい。もしゾンビ化させるようなウィルスが蔓延したら?……それをシリアスに捉えた危機的社会として描写しているからこそ、アレックスも、ケイトも、真に迫る魅力を発する。 国から“リターンドたんぱく質”の配給が停止されようとした時、アレックスは、25年来の親友にリターンドであることをカミングアウトしたことで、予想外の事態に陥ってしまう。そして、反リターンドの過激派が感染者名簿を入手してリターンド狩りをはじめる。更に出頭しないリターンドを捜査する警察の手も迫る。是非、追いつめられてゆく2人の姿を目に焼きつけて欲しい。■ © 2013 CASTELAO PICTURES, S.L. AND RAMACO MEDIA I, INC.. ALL RIGHTS RESERVED.
-

PROGRAM/放送作品
トータル・リコール
超有名なVFXシーンは必見!アーノルド・シュワルツェネッガー主演のSFアドベンチャー!
SFの普遍的テーマ、自分は起きているのか、起きている夢を見ているのか…作家フィリップ・K・ディック作品に顕著だ。そのディック作品を、ヴァーホーヴェン監督、シュワルツェネッガー主演で、娯楽SF映画化!
-

COLUMN/コラム2016.10.15
【ネタバレ】奇才ヴァーメルダム監督が描く、シッチェス・カタロニア映画祭グランプリ受賞作『ボーグマン』に見えてくるもの!
日本ではほとんど知られていない俳優たちばかりが出演し、静かに淡々とした映像が映し出されていくが、ミステリアスで得体のしれない人間を見るのは、実に興味深くて魅きつけられる。それが1人ではなく、どこからともなく集まってくるような恐ろしい集団となれば、なおさらだ。なんとも不気味で刺激的、且つアーティスティック、とはいえ最後まで飽きさせないエンタメ性も感じさせながら、シュールなテイストに満ちたオランダ=ベルギー=デンマーク合作の秀作スリラー(その不可思議なセンスからは、デヴィッド・リンチ風の匂いも感じ取れる)。 他人の土地に、無断で幾つも穴倉(ねぐらみたいなもの)を掘り、そこにホームレスのような人々が秘かに暮らしている。そんな彼らを察知した地元の人々が追い出しにかかると、一斉に穴倉から出てきて逃げ出す。 逃げる集団のリーダー格の1人は、乱れた長髪に無精ひげを生やし、大きな庭がある邸宅にやってきて、「あなたの奥さんを知っている……汚れているから、なんとか風呂を貸して欲しい」とおかしなことを強引にねだる。「妻を知っている」とテキトーなことを言う男に怒り狂った夫リシャルトは、その男を暴力的に叩きのめして追い帰してしまう。 この最初の事件が起きる前、すなわち冒頭にこんな字幕が出ていた。「そして彼らは、自らの集団を強化するため、地球へ飛来した」と……なんなんだ、この意味は!? その“彼ら”を、全編を観て分かったことを要約してみれば、他人の土地に無断侵入して、仲間と連絡を取りあって狡猾に策略を弄し、俗物的な人間を次々と殺しては、仲間(信奉者)を増やしてゆく殺人集団である。でも、どう見ても、“地球へ飛来”してきたような生物には見えない。 そして題名のボーグマンとは、謎のホームレス集団のリーダー格に見える男、或いは幹部相当の男なのか……自らをカミエル・ボーグマンと名乗っていた。「イエスは自己中のクソ野郎だ」と言い放つ彼は、大天使ミカエルを嘲笑したような名になっているのも、当然偽名だからだろうか。 ならば“地球へ飛来した”は、何らかの比喩なのか。高級住宅地に住むような富裕層を嫌う集団のようにも見えるが、リシャルト家の庭師夫婦……平凡だが性格が良さそうな人を殺害したり、リシャルト家に庭師の面接に訪れた中産階級の男たちを襲ったりしていた。そう考えると、ボーグマンらは、人間社会から逸脱し、金品や権力や名声に固執しない自由奔放さに生きつつも、彼らなりの決まりごとが確かに存在しているようだ。 カミエル・ボーグマンは、映画が始まって早々、次の標的にリシャルトと妻マリナに絞っていた。カミエルがマリナと過去に出会っていたか否かは不明だが、マリナはリシャルトが暴力で傷めつけたカミエルを気遣い、夫がいない間に風呂に入れ、大きな庭の離れにある小屋を数日間貸してあげる。カミエルは外部にいる仲間と携帯電話で連絡を取り合い、「時は来たか?」の問いに対し「まだだ」と応えていた。そしてカミエルは、秘かに邸宅に侵入しては様子を窺っていた。不思議なことに、悪夢を見て泣いていたマリナの娘イゾルデに接し、なにやら話しを聞かせていたのだ。 このイゾルデがかなり変わった子で、クマのぬいぐるみの体を裂いて中の詰め物を抜いて、代わりに土を入れていた。更に(庭師の面接にやってきた)暴力で叩きのめされた男の顔面に向け、トドメとばかりに大きなブロックを振りおろしたのだ。まるで子供が矮小な生物をいじめ、殺してしまうかのように。 すべては、カミエル・ボーグマンの悪影響なのか。それを感じさせるのが、マリナのこのセリフ。「何かに囲まれている。時々忍び込んでくるの。その温かさは心地いいけど、私たちを惑わせる……悪意を秘めているの。私には、そう感じる。後ろめたいの。私たちは、あまりにも恵まれている。罰を受けるわ」 マリナは、カミエル・ボーグマンを怖れていても、彼には抗えないほど魅かれてしまう何かがあると思っている。夫リシャルトとは180度異なり、何を考えているのかも分からないし、裕福な生活を与えてくれるわけでもない。なのに、彼のどこがいいのだろうか? やがてカミエルの肉体をも欲するようになる。彼には、女性の心を手玉に取る魔力があるのかもしれない。 リシャルト家の周辺で、ボーグマンらによって人々が殺されていくが、死体はすべて、ある池の底に遺棄されていた。謎の集団は黙々と作業をこなすように死体を処理する。死体の頭部をバケツに入れてコンクリート詰めにし、乾いたらその死体を自動車で運んで池に沈めるのだ。池の底には、コンクリート詰めのバケツの重量で、池の底に頭部が着いた逆さ死体が幾つも並んでいる。ちょっと見、水の流れに揺れる大きな水草のようにも見えるが(笑)、全て死体。これが不気味! 観終わって思うのは、カミエル・ボーグマンらカルト犯罪集団は、格差社会が生んだ恐怖の象徴なのか、富裕層に対する怒りを表現した何かか、それとも人間の代表的な欲を排してダークサイドに傾倒した人間を描きたかったのか、その意図は全くもって不明である。 従って、この映画が描きたかったことも不明瞭に映るかもしれないが、本作の魅力はそこにあると思う。観る者の想像力に刺激を与え、“地球へ飛来した”の解釈も、観た者によって異なってくるはず。筆者はこう解釈した。地続きの国の人々が抱く不安……それは外国人(英語表記だと、ALIEN)の移民や難民の流入によって、格差社会がより一層明確になっていく。移民とは感情を交わすことができないまま、貧富の格差社会が生まれるが、やがては彼らによって土地が奪われ、職を奪われ、犯罪が起きるという危惧を、ボーグマンという集団の姿を借りて表現した社会派ホラーのように見えた。まずは頭をまっさらにして、奇才アレックス・ファン・ヴァーメルダム監督が描くユニークな秀作に触れて欲しい。■ © Graniet Film, Epidemic, DDF/Angel Films, NTR
-

PROGRAM/放送作品
バラキ
[PG12相当]暗黒街に生きる男の非情な運命。チャールズ・ブロンソンが演じるマフィアの壮絶な半生!
バラキという実在のマフィアが明かす闇社会の恐るべき秘密。『セルピコ』と同じ原作者がこれを取材したノンフィクションを、アクションやサスペンスに定評のあるテレンス・ヤング監督が映画化した実録極道モノ。
-

COLUMN/コラム2016.08.06
【未DVD化】タイトルに「大」が付くジェラール・ウーリー監督作はフレンンチ・コメディのなかでもとびきりの面白さの証し〜『大頭脳』〜
1969年8月9日日本公開なので、おそらく1961年生まれの僕は8歳だった。育った岩手県盛岡市には映画館が密集する映画館通りというのがあり、きっとそこのど真ん中にあった盛岡中劇で観たと思う。1968年4月日本公開の、フランクリン・J・シャフナー監督の『猿の惑星』はのちにテレビの洋画劇場で観たので、ラストに自由の女神像を初めて観たのも(『猿の惑星』のラストで驚愕させるのも自由の女神像だった)、この映画だったはずだ。いまでも鮮明に記憶している。 ともかく、デヴィッド・ニーヴン演じるブレインが、脳みそが詰まっていると見えて、事あるごとにカックンと首を傾けるのがおかしかった! ジェラール・ウーリー監督作品には、『大追跡』(1965) 『大進撃』(1966) 『大頭脳』(1969) 『大乱戦』(1971) 『大迷惑』(1987) と「大」が付くタイトルが多かったが、フランス映画のコメディのなかでもそれは、とびきりの面白さの証しだった。 脚本チーム、ジェラール・ウーリー監督と、『大追跡』『大進撃』のマルセル・ジュリアンと、『ラ・ブーム』(1980) のダニエル・トンプソンが紡いだ物語は、イギリスで実際に起こった大列車強盗事件を背景にした、軽いタッチのコメディ・サスペンス。NATOの軍資金、14か国の紙幣で1,200万ドルを、「悪党」と「野郎」と「奴ら」が三つ巴で同じ日、同じ時刻、同じ場所で狙うというものだった。 その「悪党」とはイギリスの紳士らしい列車強盗事件の首謀者で、その名も「ブレイン(頭脳)」というすこぶる付きの切れ者、イギリスのデヴィッド・ニーヴンが演じている。 その「野郎」とはかつてのブレインの共犯者で、相変わらずの汚い野郎ぶりで笑わせてくれる、美しい妹ソフィアと病的に溺愛するシシリーのマフィアのボス、スキャナピエコ。アメリカのイーライ・ウォラックが演じている。 その「奴ら」とはアナトールとアルトゥールのコンビ。アナトールは今はタクシー運転手だが、その秘密軍資金をいただこうと刑期満了の4日前にかつての相棒アルトゥールを脱獄させるのだ。フランスのジャン=ポール・ベルモンドとブールヴィル(『大追跡』『大進撃』といったウーリー監督作品常連のコメディアン) が演じている。 かくして大金は、パリからブリュッセルへ、ロンドンからシシリーを通ってニューヨークまで行ってしまう。大西洋上の豪華客船の船上に札束は舞い、三つ巴の戦いは引分けに終わる。ブレインは、敵ながら天晴れとばかりに、次の大仕事でアナトールとアルトゥールと手を組もうとする。で、ちゃんちゃんと終わる。 素晴らしいドタバタコメディだ。『八十日間世界一周』(1956) のデヴィッド・ニーヴンも、『続・夕陽のガンマン/地獄の決斗』(1966) のイーライ・ウォラックも最高だが、『リオの男』(1963) のジャン=ポール・ベルモンドと『大進撃』(1966) のブールヴィルのコンビがとぼけた味で、抱腹絶倒なのだ。 この英米仏の素晴らしい配役が、傑作のカギとなった。また、紅一点で活躍するスキャナピエコの妹ソフィアを演じるのはイタリア人女優シルヴィア・モンティ。黒いビキニ姿が艶かしい。その彼女がブレインに恋しちゃうので、面白いことに、マフィアのボスの嫉妬の炎は燃え盛る。彼女の存在そのものはもしかしたら、ハワード・ホークス監督作品『暗黒街の顔役』(1932) のトニー・カモンテ(ポール・ムニ) が溺愛した妹チェスカー(アン・ドヴォラーク) を狙ったのかもしれない。 そして面白いのは、冒頭にブレインが現金強奪の計画を仲間に説明するシークエンス。なんと、その説明にはカタカタ鳴る映写機を使うのだ。そこで上映されるのは計画の進行を表すアニメーション。軽快なコーラス(音楽がいい) 入りで流れるそのアニメのデヴィッド・ニーヴンは、走る列車の屋根をかっこよく駆け抜けたりする。ところが実際の本番ではアニメとは大違いで、ニーヴンときたら列車の屋根をよろよろと歩く始末。このギャップが大笑いだった。 音楽を担当したのはフランス人作曲家ジョルジュ・ドルリュー。『ピアニストを撃て』(1960) 『突然炎のごとく』(1962) 『柔らかい肌』(1963) 『恋のエチュード』(1971) 『私のように美しい娘』(1972) 『映画に愛をこめて アメリカの夜』(1973) 『逃げ去る恋』(1978) 『終電車』(1980) 『隣の女』(1981) 『日曜日が待ち遠しい』(1982) といったフランソワ・トリュフォー監督作品の音楽はどれも珠玉の名作で、とんでもなく好き。エンニオ・モリコーネを別格としてジョン・バリーらと並んで最も好きな映画音楽の作曲家のひとり。トリュフォー以外にも、ジャン=リュック・ゴダールの『軽蔑』(1963)、ケン・ラッセルの『恋する女たち』(1969)、ベルナルド・ベルトルッチの『暗殺の森』(1970)、フレッド・ジンネマンの『ジュリア』(1977)、ジョージ・ロイ・ヒルの『リトル・ロマンス』(1979)、オリヴァー・ストーンの『プラトーン』(1986) といった傑作揃いの音楽を手がけている。ジェラール・ウーリーの『大追跡』(1965) も手がけているが、フィリップ・ド・ブロカとも『リオの男』(1963) 『カトマンズの男』(1965) 『まぼろしの市街戦』(1967) 『ベルモンドの怪人二十面相』(1975) などを手がけており、フランスのコメディにはなくてはならない人だった。 この『大頭脳』は1970年半ばにはテレビの洋画劇場などでかかったものだった。DVD化を望みたい。■ © 1969 Gaumont (France) / Dino de Laurentiis Cinematografica (Italie)
-
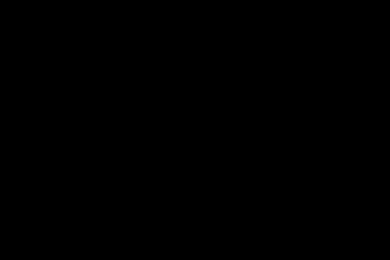
PROGRAM/放送作品
クストー監督3部作の見どころ
-
-
-

COLUMN/コラム2016.08.03
『荒野の用心棒』で金の鉱脈を掘り当てたレオーネ監督&イーストウッドがさらなるお宝を求めて突き進む『夕陽のガンマン』+『続・夕陽のガンマン』
1.ほんのひと握りのドルのために ― 『荒野の用心棒』 筆者が今回ここで紹介すべき映画は、『夕陽のガンマン』(65)と『続・夕陽のガンマン』(66)の2本だが、そのためにはやはりまず、両者に先立つ『荒野の用心棒』(64)にご登場願わなくては、どうにも話が進めにくい。 ほんのひと握りのドルのために。すべてはそこから始まった。 当時、全米のTV西部劇シリーズ「ローハイド」(59-66)に準主役でレギュラー出演し、お茶の間の人気を得るようになってはいたものの、番組のマンネリ路線に飽きを覚えていたクリント・イーストウッドのもとに、1本の映画への出演依頼が思いがけず外国から舞い込み、彼が半ば物見遊山でヨーロッパへと旅立ったのは、1964年のこと。 ところが、当初の別題から先述の「ほんのひと握りのドルのために」という原題に最終的に変わる、何とも素性が怪しげでいかがわしいその多国籍映画 ― 本来はアメリカの専売特許たる西部劇を、スペインの荒野をメキシコ国境の無法の町に見立てて撮影した、イタリア・ドイツ・スペインの3カ国合作による低予算の外国製西部劇で、主演のイーストウッドを除くと、イタリア人を中心にヨーロッパの連中で固められたキャスト・スタッフの大半のクレジットはアメリカ人を装った別人名義、しかも、日本の時代劇(改めて言うまでもなく『用心棒』(61 黒澤明))の物語を、著作権を正式に得ないまま勝手に翻案・盗作したせいで、やがて訴訟騒ぎにまで発展する ― 『荒野の用心棒』が、同年のイタリア映画界最大のヒット作となったのをはじめ、当事者たちすら予想だにしなかった世界的ヒットを記録して、その名も“マカロニ・ウェスタン”(外国での呼び名は“スパゲッティ・ウェスタン”)ブームに火をつけ、以後、同種の外国製西部劇が続々と生み出されるようになるのだ。以前、本欄で『黄金の眼』(67 マリオ・バーヴァ)を紹介した際にも説明したように、1960年代は、御存知『007』(62- )シリーズの登場と共に、スパイ映画が各国で作られたり、また日本でも日活の無国籍アクションが量産されたりするなど、娯楽映画における異文化間の移植培養、雑種交配=ハイブリッド化が汎世界的に同時進行しつつあった。 監督のセルジオ・レオーネと主演のイーストウッドの双方にとっても、『荒野の用心棒』は一大出世作となった。ただし、レオーネは、プロデューサーたちと事前に結んだ不利な契約のせいで、映画の大ヒットによるご褒美の分け前には一切与ることが出来ず、また、盗作問題を巡る訴訟騒ぎで同作の全米公開が1967年まで先延ばしにされたせいで、イーストウッドの方も、自らの成功をなかなか実感できずにいた。2人は再度コンビを組み、柳の下の二匹目のどじょうを狙うことになる。もう少々のドルのために、と。 2.もう少々のドルのために ― 『夕陽のガンマン』 かくして、『夕陽のガンマン』がいよいよ登場することになる。映画の製作費は60万ドルと、『荒野の用心棒』の20万ドルの3倍に跳ね上がり、イーストウッドの出演料も、前作の1万5千ドルから5万ドルプラス歩合へと大幅にアップ。前作で、薄汚れたポンチョに身を包み、無精髭のニヒルな面構えに、短い葉巻を口の端にくわえこんだ独特の風貌とスタイルで、正体不明の流れ者の雇われ用心棒をどこまでも寡黙かつクールに演じた彼は、今回もそのトレードマークをそっくり受け継いだ上で、新たな役どころに挑むことになる。「生命に何の価値もないところでは、時に死に値段がついた。“賞金稼ぎ”が現れた由縁である」と、オープニングのクレジット紹介に続いて『夕陽のガンマン』の物語世界の初期設定が字幕で示される通り、ここでイーストウッドは賞金稼ぎの主人公を演じることになるのだ。 マカロニ・ウェスタンが、本来アメリカ映画の長年の伝統と歴史を誇る西部劇を、それとはおよそ無縁なヨーロッパの地に移植して作り上げられたまがい物の産物であることは既に述べたが、そこでレオーネ監督とイーストウッドが行なった大胆不敵で革新的な実験のひとつが、高潔な正義のヒーローが悪を打ち倒すという、従来の西部劇に特有の勧善懲悪調の道徳劇のスタイルをばっさり切り捨てることだった。既に『荒野の用心棒』の主人公自体、『用心棒』からの無断借用とはいえ、従来の正統的なアメリカ製西部劇の正義のヒーローとは程遠い、ダーティなアンチ・ヒーロー像を打ち立てていたが、この『夕陽のガンマン』でイーストウッドが演じる主人公の役柄は賞金稼ぎに設定され、善悪という道徳的な価値判断や倫理観よりも、あくまで賞金目当ての欲得と打算がその行動原理の前面に据えられる。こうして、血なまぐさい暴力が支配する無法の荒野で、主人公も含めてエゴや私利私欲を剥き出しにした連中が互いに裏切り騙し合いながら相争うさまを、痛烈なブラック・ユーモアと残虐なバイオレンス描写を随所に交えながら冷笑的に描く、レオーネならではの傍若無人、問答無用の娯楽西部劇世界が、本作でより一層華麗に展開されることになる。 『荒野の用心棒』では、互いに相争う2組の悪党どもの対立を、イーストウッド演じる主人公が一層煽り、けしかけながら、双方を壊滅状態に追い込む様子を描いていたのに対し、『夕陽のガンマン』では、共に腕利きの同業者にして宿命のライバルたる2人の賞金稼ぎが、時に相争い、時には紳士協定を結んで互いに協力しながら、いずれも多額の懸賞金のついた悪党どもとその親玉を次第に追い詰めていく様子が描かれる。かくのごとく、三つ巴の戦いを映画の物語の根幹に据えることが、どうやらこの頃のレオーネのお好みのフォーマットであったことが見て取れるだろう。 イーストウッドが賞金稼ぎの主人公を、そしてジャン・マリア・ヴォロンテが『荒野の用心棒』に引き続いて悪党の親玉を演じるのに加え、今回、イーストウッドのライバルたるもうひとりの賞金稼ぎ役には、どこか猛禽類を思わせる精悍な顔立ちと眼光鋭い目つき、そして黒装束に身を包んだスレンダーな長身が印象的なリー・ヴァン・クリーフが起用され、風格に満ちた強烈な個性と存在感を存分に披露。相手との距離を充分に見極めた上で沈着冷静に標的を仕留めるその確かな銃の腕前で、映画の中盤、彼がイーストウッドと互いに相手の帽子を撃ち合いっこする場面は、今日改めて見直すと、何とも稚気丸出しのくどい演出で多少ダレるが、筆者が小学生の頃、最初にテレビで見た時は、こいつはまるでマンガみたいで面白いや、と興奮したものだっけ…。 そして、紹介の順序がすっかり後になってしまって我らが偉大なマエストロには大変申し訳ないが、これらの要素にさらに御存知エンニオ・モリコーネの比類なき映画音楽が加味されて、『夕陽のガンマン』でレオーネ独自の世界は早くも一つの完成を見ることになる。実はかつて小学校時代の同級生だったというレオーネと初めてコンビを組んで、モリコーネが『荒野の用心棒』につけたサントラ自体、口笛にギターやコーラス、そして鐘や鞭の音などを多彩に組み合わせた斬新なアレンジで、マカロニ・ウェスタンの音楽はかくあるべしと、以後の基調的なサウンドを一挙に決定づけた超絶的傑作だったわけだが、本作でモリコーネの音楽は、物語とより有機的に一体化されてドラマを情感豊かに彩ることになるのだ。 とりわけ、ヴァン・クリーフとヴォロンテの間に実は深い因縁があったことを、懐中時計から流れるオルゴールのメロディが何よりも雄弁に物語り、その印象的な旋律をバックに、彼らが宿命の対決を繰り広げるクライマックスの円形広場での決闘場面は、やはり何度見てもスリリングで面白い。ここでイーストウッドは、半ば主役の座をヴァン・クリーフに譲り、公正なレフェリー役として2人の決闘に立ち会うことになるが、レオーネ監督は、この円形広場での決闘場面を改めて自ら反復・変奏し、今度はいよいよ三つ巴の戦いの決着の場として、よりけれんみたっぷりに描き出すべく、『荒野の用心棒』『夕陽のガンマン』と共に3部作を成す、次なる壮大な野心作『続・夕陽のガンマン』に挑むことになる。 3.ドルは充分稼いだ。さて、しかし…マカロニ・ブームの頂点を極めたバブル巨編 ― 『続・夕陽のガンマン』 『夕陽のガンマン』が『荒野の用心棒』をも上回る大ヒットで2年連続イタリア国内の興収記録第1位に輝いたのを受けて、『続・夕陽のガンマン/地獄の決斗』の製作費は120万ドルと、『夕陽のガンマン』の60万ドルからさらに倍増し、イーストウッドの出演料も25万ドルプラス歩合と、前作から約5倍にアップ。倍々ゲームのようにしてイケイケで駒を進めてきたレオーネ監督はここで、作品の長さも約3時間に及ぶ、マカロニ・ウェスタン史上空前のスケールの超大作を生み出すこととなった(長尺が影響したのか、『夕陽のガンマン』の興収記録には及ばなかったものの、本作もやはり大ヒットして、みごと3年連続イタリア国内の第1位に輝いた)。 映画の原題は既によく知られている通り、「いい奴、悪い奴、汚い奴」で、賞金稼ぎの「いい奴」をイーストウッド、冷酷非情な殺し屋の「悪い奴」を『夕陽のガンマン』の役柄とは好対照をなす形でヴァン・クリーフ、そして首に賞金の懸かったお尋ね者の「汚い奴」には、かのアクターズ・スタジオ出身の実力個性派イーライ・ウォラックが起用され、三者三様、互いの持ち味と個性を競い合う。ただし先にも説明したように、勧善懲悪の世界とは無縁のレオーネ映画にあって、この3人は、その呼び名の通り、善玉と悪玉などにくっきり色分けされている訳では無論なく、「いい奴」役を割り当てられたイーストウッドも含めて、いずれもひと癖もふた癖もある悪党どもばかり。そんな彼らが、ふとしたきっかけで知った某所に眠る20万ドルもの財宝をめぐって決死の争奪戦を繰り広げる様子を、レオーネ監督は、南北戦争時代のアメリカを物語の舞台に、圧倒的な物量作戦で戦闘シーンをスペクタクル風に再現したり、コヨーテの遠吠えを模したモリコーネの強烈な主題曲を織り交ぜたりしながら、どこまでも悠然としたペースで描いていく。 そして、物語の大詰め、この3人の主人公たちが、いよいよ三つ巴の決闘に挑むべく、円形広場で3方に分かれて対峙する、名高いクライマックスが訪れることになる。ここでレオーネ監督は、3人それぞれの顔の表情やガンベルトにかけた手のクロースアップを、これでもかとばかりに何度となく繰り返しクロスカッティングさせ、そこへさらにモリコーネ独特の音楽がバックにかかり、トランペットの音色やオーケストレーションが次第に高鳴るにつれ、いやがうえにも映画はドラマチックに盛り上がる……ことはまあ確かなのだが、その一方で、本来なら一瞬であるはずの決闘直前の3人の睨み合いの息詰まる緊張した時間が、どこまでもズルズルと非現実的に引き延ばされるのに付き合わされるうち、すっかりダレて疲れてしまい、一体これ、いつまで続くんだろう? とふと我に返って思いをめぐらす瞬間が訪れることも、また確かだ。 『続・夕陽のガンマン/地獄の決斗』は、御存知あのクエンテン・タランティーノが、オールタイム・ベストの1本としてしばしばその名を挙げて再評価が進み、公開当時よりもむしろ近年の方が、映画ファンたちの間では人気と支持が高まっている。それは無論、承知の上で、しかし筆者自身、子供の頃から何度も目にしているからこそ(2002年、フィルムセンターで開催された「イタリア映画大回顧」特集での、日本初となるイタリア語復元版でのスクリーン上映も見に行ったし、DVDのアルティメット・エディションもしっかり買って、ひと通り見ている)、あえてここで言わせてもらうならば、上記の場面が象徴的に示しているように、この映画はやはり、全体的にどうも妙に肥大化して弛緩した、バブリーで冗漫な一作、という印象はぬぐえない。もちろん、それなりに面白くて楽しめることは充分認めるんだけどね…。 『夕陽のガンマン』を手始めに、お互いにろくに言葉も通じぬままたて続けにコンビを組み、マカロニ・ウェスタン3部作を生み落としたイーストウッドとレオーネ監督だが、一作ごとに自らの野心と欲望を肥大化させ、まるでデヴィッド・リーンばりの巨匠を気取って大作路線を突き進むレオーネに次第に違和感を覚えるようになったイーストウッドは、『続・夕陽のガンマン』を最後に、ついに彼と袂を分かつことになる。そして、人気スターとなってアメリカに凱旋帰国を果たしたイーストウッドは、やがてドン・シーゲル監督という新たな師匠と出会い、より簡潔で無駄のない引き締まった演出法を彼から伝授された上で、自らも映画作家となり、さらなる高みを目指して険しい道=マルパソを歩むことになるのである。■ FOR A FEW DOLLARS MORE © 1965 ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A.. All Rights Reserved GOOD, THE BAD AND THE UGLY, THE © 1966 ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A.. All Rights Reserved
-

PROGRAM/放送作品
特番「監督ジョン・カサヴェテスの2つのファミリー」
アメリカ・インディペンデント映画の父、監督ジョン・カサヴェテスの魅力を紹介するミニ番組。
アメリカ・インディペンデント映画の父と呼ばれ、世界中の映画人に愛され影響を与え続ける、監督ジョン・カサヴェテス。自身の人生、そして家族や仲間たちとの映画愛に満ちた制作背景を通し、彼の映画の魅力に迫る。
-

COLUMN/コラム2016.07.08
“高尚な趣味のOL”御用達の退屈文芸監督と思ったら大間違い。ジョー・ライト監督、その異常ともいえる美意識の高さと、狂気じみた映像へのこだわり〜『アンナ・カレーニナ』〜
ジョー・ライトという監督がマニアックに語られることが少ないのはなぜなのか。長編デビュー作がジェーン・オースティンの恋愛小説が原作の『プライドと偏見』(2005)であったり、『つぐない』(2007)、『アンナ・カレーニナ』(2012)と文芸路線が多いことから高尚な趣味のOL御用達だと思われているのだろうか(高尚な趣味のOLという存在自体がもはやファンタジーだが)。 『プライドと偏見』は2000年代でも屈指の「衝撃デビュー」だったと思うのだが、日本公開時の宣伝は完全に女性に向けたラブストーリー扱いで、ジョー・ライトの狂気じみた映像へのこだわりは語られることが少なかった。 いや、もちろん『プライドと偏見』はラブストーリーとしても素晴らしい。その一方で、映画好きなら垂涎の映像表現や演出が詰まっていることが伝わらないままスルーされてしまった印象がある。 ジョー・ライトの最大の個性は、あらゆることを「画と音」で伝えようという強迫観念に似た執念である。『プライドと偏見』は出会った瞬間からそりが合わない男女の恋を描いたラブコメの原典だが、18世紀当時のイギリスの階級社会や文化が登場人物の思考や立ち位置を決定づけている。ライトが試みたのは、コミュニティのヒエラルキーの全容と男女の誤解、にもかかわらず芽生える恋心のはじまりをひっくるめて、舞踏会のワンシーンだけで表現してしまうことだった。 映画序盤でかなりの尺をもって描かれる舞踏会は長回しのカメラと出演者の演技が緻密に振り付けられ、シーンまるごとが壮大な群舞となった。これほどの情報量をビジュアルの力で伝えきった豪腕に「天才監督あらわる!」と興奮したことが忘れられない。 監督二作目の『つぐない』は幼い少女の誤解によって引き裂かれてしまう恋人たちを描いたメロドラマだが、第二次世界大戦の激戦「ダンケルクの撤退」を描いた5分半もの長回しで語り草になった 英仏33万人の将兵がドーバー海峡を渡ってイギリスに退却した最前線での混沌を圧倒的な物量で描いた壮麗なワンショットは、映画全体のトーンからハミ出ているがゆえに運命を翻弄する「戦争」の巨大さを象徴していた。 長回しといえばデ・パルマ、最近ではキュアロンかイニャリトゥの名前が挙がるのが通例だが、ライトは『つぐない』に限らずどの監督作でも凝りに凝った長回しを披露している。本人が「ひけらかすのが好きなんだ」と自嘲まじりに笑い飛ばすトレードマークであり、シーンのメイキングだけでも一冊の本ができてしまいそうである。 また「音楽」への執着もジョー・ライト作品の特徴だ。前述の舞踏会は言うに及ばず、『つぐない』の恋文を打つタイプライターがビートを刻みテンションを高めていくモダンさは、ありふれた「文芸映画」のイメージを軽々と飛び越える。『路上のソリスト』(2009)はまさに音楽家の物語だったし、成功作とは言えないにせよ『PAN~ネバーランド、夢のはじまり~』(2015)でニルヴァーナをぶっ込んだ遊び心も強烈だった。 現時点でのジョー・ライトの最高傑作を決めるつもりはないが、『アンナ・カレーニナ』はジョー・ライト的映画術がこれでもかと詰め込まれた、集大成と呼ぶべき濃密作であることは間違いがない。 原作はロシアの大文豪トルストイの代表作。タイトルだけは誰もが聞いたことがあるはずだが、知名度のわりに概要を知っている人は少ないので簡単に説明しておこう。 舞台は1870年代の帝政ロシア。ざっくり言えば上流階級の貞淑な若妻アンナ(キーラ・ナイトレイ)が、イケメン将校ヴロンスキー(アーロン・テイラー・ジョンソン)との不倫愛にのめり込み破滅へと突き進んでいく悲劇である。 若い農場主リョーヴィン(ドーナル・グリーソン)と若い娘キティ(アリシア・ヴィキャンデル)の純朴な恋模様や、アンナの兄の浮気騒動といったサブプロットもが同時進行するが、基本はアンナと愛人と夫の三角関係の愛憎劇。ただし当時のロシア社会への批判、トルストイの理想と現実にまつわる考察が込められていて、当然ながらただの不倫メロドラマではない。 トルストイの原作自体が文学史上の傑作とされており、過去にはグレタ・ガルボ、ヴィヴィアン・リー、ソフィー・マルソーらの主演で何度も映像化されている。言わばさんざん手垢が着いているからこそ、ライトは前代未聞のアプローチを見つけ出した。240に上るシーンの大半を、たったひとつのセットで撮ってしまったのだ。 企画当初はロシアで撮影しようとロケハンにも行ったが、現地で「ここで『アンナ・カレーニナ』を撮るのは7本目ですね」と言われて方針を180度変えた。朽ちかけた劇場のセットを建てて、シーンの違いを舞台装置によって表現しようというのだ。 むろん劇場での演劇をそのまま撮影するわけではない。ひとつの建物がまるごと、アンナたちが暮らしているロシア社会に見立てられているのである。ステージや客席は華やかな社交や場となり、天井裏はうらぶれた路地や貧者の家になる。スケートリンクから競馬のパドックまで、衣装の早替えのようにシーンが移り変わっていく様はまるで魔法を見ているかのようである。 セットを「劇場」にしたのには明快な理由がある。登場人物の誰もが社会という枠に押し込められて、与えられた役割を演じながら生きているから。アンナは虚飾に満ちた世界から逃れるようにヴロンスキーとの逢瀬にすがりつくが、もがけばもがくほど世間の反感を買って生きるスペースが狭まっていく。劇中に「観客」が登場しないのは、彼らは出演者であると同時にお互いを見張る観客でもあるからだ。 ギミックを凝らした過剰さに眩暈を起こす人もいるかも知れないが、映像や美術の端々に込められた深い寓意には戦慄すら覚える。例えばアンナの息子の寝床はまるで額縁の中のようにデザインされていて、兄の家の子供たちの部屋は大きなドールハウスだ。まるで大人の都合で観賞用に閉じ込められた「箱の中の箱」である。 ライトがインスピレーションを得たのは子供の頃に夢中だった人形劇だそうだが、誰もが大きななにかに操られていると感じさせることでミニマムな空間からマクロな視点が生まれる。さらに盟友ダリオ・マイアネッリの音楽とシディ・ラルビ・シェルカウイの振付が加わり、流麗で饒舌な映像美に昇華されているのだ。 『プライドと偏見』をさらに進化させた舞踏会のダンスシーンは本作の白眉だが、直接ダンスが絡まない場面での手や首の優雅な動きにも目を凝らして欲しい。自然体とは対極にある誇張された動きだが、いかに雄弁に気持ちを語っていることか。本音をぶちまけることが許されなかった時代背景が、異常ともいえる美意識の高さに昇華されていて息が詰まるほどだ。 とはいえ同じことを現代劇でやるのは難しかっただろう。こういう形で演劇を取り入れた先例として木下恵介の『楢山節考』(1958)、エリック・ロメールの『聖杯物語』(1978)、ラース・フォン・トリアーの『ドッグヴィル』(2003)などが挙げられるが、いずれも時代物であり、虚構性を高めることで寓話としての強度を高めている。 『アンナ・カレーニナ』がそれらの先達と違うとすれば、キャラクターを戯画化していないことではないか。ひとりひとりをシンボライズするのでなく、矛盾に満ちたグレーな人間としてリアルに描く。しかしビジュアルや演技は徹底的にアンリアルという倒錯感を、ジョー・ライトという才気あふれる映画監督の気概と一緒に楽しんでいただきたいと思う。■ ©2012 Focus Features LLC