検索結果
-

PROGRAM/放送作品
さよならをもう一度
イングリッド・バーグマン主演、半世紀前の“アラフォー”ストーリー
原作は、フランソワーズ・サガンの4番目の長編小説「ブラームスはお好き」。“いつまでもお若いですね”という言葉が向けられる自分自身に虚しさを感じ、寄る辺なさに悩むポーラの揺れ動く心を追う。
-

COLUMN/コラム2017.07.03
個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年7月】うず潮
1988年当時、フランス領であったニューカレドニアで先住民族による独立紛争事件が発生。この事件の交渉役を任された国家憲兵隊大尉の告発手記をもとに、『クリムゾン・リバー』のマチュー・カソヴィッツが監督・主演を務め、入念なリサーチを重ねて完成まで10年も費やした意欲作です。フランス本国で現職のミッテラン大統領VSシラク首相による、熾烈な大統領選のさなかに起きた紛争事件の真相を描いています。両陣営から繰り出される票集めを見据えた命令に、揺らぐ現場の臨場感をリアルに描き出しているので、まるで当事者として参加しているように、グイグイと映画の中に引き込まれていきます。「自分だったらどう判断するのか?」と問いかけずにはいられない作品です。是非ご覧頂きたい1本!■ © Nord-Ouest Films – UGC Images – Studio 37 – France 2 Cinéma
-

PROGRAM/放送作品
エンゼル・ハート
“悪魔のバイブル”と称された小説を映像化。スタイリッシュな映像美が秀逸なオカルト・ミステリー
“悪魔のバイブル”と評された戦慄オカルト小説を、社会派サスペンスが得意なアラン・パーカーが、フィルム・ノワールを思わせるスタイリッシュな映像美で映画化。ロバート・デ・ニーロの怪演も必見。
-

COLUMN/コラム2018.03.10
史実に忠実な局地戦映画『ズール戦争』は歴史的大傑作!
1800年代初頭に南アフリカに進出したイギリス帝国。先行して入植していたボーア人(オランダ系の植民者)はイギリス帝国の支配を嫌い、新たな入植地を求めてグレート・トレックと称される北上を開始した。そこには強大な戦力を誇るズールー王国が存在し、ボーア人たちとの血で血を洗う抗争を展開。1835年、ボーア人はブラッド・リバーの戦いでズールー族に勝利を収めると、この地にナタール共和国を建国した。しかしこのナタール王国もボーア人の独立を快く思わないイギリス帝国の侵攻によって、わずか4年という短い期間で崩壊してしまう。 その頃、ズールー王国ではボーア人に敗れたディンガネ国王は威信を失って失脚。後継のムパンデ国王の息子2人が後継の座を争って対立し、この内乱に勝利したセテワヨが国王に即位した。セテワヨは軍制を再編し、マスケット銃(先詰式の滑腔式歩兵銃)を装備した小銃部隊を編成するなど、軍の近代化を推進。これは拡大を続けるイギリス帝国を迎え撃つ準備であった。 セテワヨ自身はイギリス帝国との関係を良好に保とうとしていたが、イギリス帝国の原住民問題担当長官のシェプストンが高等弁務官フレアに対し、ズールー王国はイギリス帝国のアフリカ覇権最大の障害であることを報告。南アフリカ軍最高司令官のチェルムスフォード中将もこの意見に同意し、南アフリカのイギリス軍は着々とズールーとの戦争の準備を行うことになる。 1878年、高等弁務官のフレアは2人のズールー兵がイギリス領の女性と駆け落ちして越境したことを口実に、ズールー王国に対して多額の賠償を請求。ズールー王国がこれを拒否すると、フレアはズールー王国側に最後通牒を提示。13か条に及ぶこの最後通牒は、ズールー王国側が絶対に飲めない条件を列挙したものであり、ズールー王国のセテワヨ王はこれに対する明確な回答をせずにいた。 1879年1月、チェルムスフォードはヨーロッパ兵とアフリカ兵からなる17,100名の部隊を率いて、ズールー王国へと侵入を開始。迎え撃つズールー軍は4万の兵力。軍の近代化・火力化は未完だったが、イギリス帝国軍を上回る兵力と、圧倒的な士気の高さ、そして地の利を活かした機動力を持つ強力な部隊であった。 実戦経験の少ないチェルムスフォード中将は、部隊を複数に分割。そのため個々の部隊の兵力は手薄となり、第三縦隊1,700名はイサンドルワナに野営地を構築。そこに突如現れた約2万人のズールー軍が突撃を敢行し、“猛牛の角”と呼ばれる連続突撃戦術によってイギリス軍を全滅させてしまう。イサンドルワナの戦いはズールー軍の精強さをいかんなく発揮した戦いであり、ズールーの名を世界に轟かせることになったエポックな勝利であった。 前置きが長くなったが、ここからが今回ご紹介する『ズール戦争』(64年)の舞台となるロルクズ・クリフトの戦いが始まることになる。 1月22日にイサンドルワナの戦いでイギリス軍を撃破したズールー軍は、翌23日未明に約4,000人の部隊をイサンドルワナから15km離れたロルクズ・クリフトにある伝道所跡に駐屯するイギリス軍守備隊に突撃させた。イサンドルワナの敗戦を聞いたアフリカ兵が逃亡してしまい、ロルクズ・クリフトの守備隊の人数はわずか139人。30倍以上の敵軍に囲まれ、ろくな防御設備も無いロルクズ・クリフトの守備隊だったが、新任将校のチャード中尉指揮の下でズールー軍の猛烈な突撃を何度も撃退することに成功。イサンドルワナから退却してきたチェルムスフォードの本隊が接近したことから、2日間昼夜に渡る波状攻撃を繰り返していたズールー軍はようやく撤退した。ロルクズ・クリフトの戦いでイギリス人は27人が死傷。対するズールー軍は351人が戦死した。 このロルクズ・クリフトの戦いを描く『ズール戦争』は、監督のサイ・エンドフィールドがロルクズ・クリフトの戦いに関する記事を読み、インスピレーションを受けたことから始まる。エンドフィールドはこの映画の企画を友人で俳優のスタンリー・ベイカーに持ち込み、ベイカーはプロデューサーとして資金調達を実施。最低限の資金が集まると、早速映画製作を開始した。 集まった制作費はわずか172万ドル(メイキングでは見栄を張っているのか、260万ドルと称している)。そこでエンドフィールドは友人の俳優とスタッフを集めて制作費を抑え、さらにセット構築費を削減するために南アフリカでのオールロケーションを実施した。現地ではズールー族の協力を得て、1,000人以上のエキストラが参加。演技初体験のズールー族とのコミュニケーションをとるために、スタッフとキャストは積極的にズールー族とコミュニケーションを取る努力を行っている。しかし当時の南アフリカではアパルトヘイト法が存在しており、本作の脚本がズールー族を勇敢で敬意を受けるに足る存在として描いていることもあり、南アフリカの公安が撮影クルーの監視を行っている中での撮影となった。 『ズール戦争』は公開されるや興行収入は800万ドル、イギリス市場では過去最大級の記録的な大ヒット作品となった(映画の舞台となった南アフリカでは、映画に参加した一部のエキストラ以外の黒人はながらく観ることの出来ない映画となっていた)。本作はイギリス人の琴線に触れる作品となっており、毎年年末年始にTVで放映されるという『忠臣蔵』のような定番映画となっている。 本作の素晴らしさは、まず映画をロルクズ・クリフトの戦いのみを描いたことであろう。ズールー戦争全体を描けば、イギリス帝国の侵略戦争、黒人差別、虐殺といったセンシティブなキーワードに触れざるをえず、価値観が目まぐるしく変わる現代においては観る者によって評価を大きく変えてしまうポイントとなる。しかし本作では、どちらが正義でどちらが悪という描き方ではなく、純粋にひとつの戦いを史実に沿って描く作品とし、余計なものを極力そぎ落としている点が、後世でも高い評価を受けている大きな要因だろう。 また驚くべきことに1960年代の脚本にも関わらず、ズールー族を野蛮な原住民ではなく、特殊な美意識を持った尊敬すべき集団として描いている点も注目。逆にイギリス軍側は、侵略者でも犠牲者でもなく、絶望的な状況に放り込まれたごく普通の青年たちとして描くことで普遍性をゲットすることに成功している(フック二等兵の描き方には子孫からのクレームもあったが)。 また史実を忠実に再現し、緊急の防御陣地設営、長篠の戦いよろしくマルティニ・ヘンリー銃(5秒に1発射撃可能)での三段射撃で間断なく制圧射撃を繰り返す様子や、ズールー族側の“猛牛の角”作戦など、緻密なリサーチが行われたことが映画の端々から感じられ、マニアックな視点でも信頼性が非常に高い作品となっている。 他にも予算不足に起因したオールロケーションも、結果的には大成功。アフリカの広大な風景はセットやマットペイントでは決して再現できなかったであろう。音楽を担当したジョン・バリーも流石のお仕事だ。 そして本作で存在感を示したのは、準主役のマイケル・ケイン。ながらく下積みを続けていたケインは、オーディションの末にフック二等兵役となっていた。しかしブロムヘッド少尉役の俳優が降板し、現地入りした俳優の中で一番貴族出身将校っぽく見えるケインがブロムヘッド少尉役に抜擢。初めての大役で戸惑うケインの立ち位置と、初めての戦場で戸惑うブロムヘッドの立ち位置が見事にシンクロして高い評価をゲット。ケインは『国際諜報局』(65年)で世界的スターへと上り詰めていくことになる。 本作は英国映画協会が選ぶイギリス映画ベスト100でも、30位に入る作品。イサンドルワナの敗戦を描く『ズールー戦争』(79年)も併せて観ておきたい作品である。■ TM, ® & © 2018 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.
-
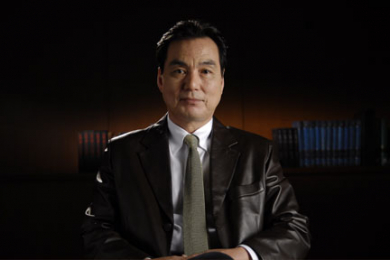
PROGRAM/放送作品
シネマの中へ 月間総集編
長塚京三の案内で、クラシック映画を楽しむためのポイントを予習する、ミニ解説番組の総集編
毎週土曜あさ10時の「赤坂シネマ座」。この枠で取り上げる、映画史に残る名作たちの魅力を、俳優・長塚京三さんが紹介。クラシック映画の敷居の高さを取り払う様々な予備知識で、本編が120%楽しくなる。
-

COLUMN/コラム2017.04.09
Mr.ズーキーパーの婚活動物園
「動物園の飼育員となんて結婚できないわ!」恋人ステファニーにプロポーズをするも、そんな捨てゼリフでフラれたグリフィン。それから5年。仕事に打ち込んだ彼は飼育係のリーダーになっていたものの、心は打ち砕かれたままだった。そんなある日、グリフィンは兄の結婚披露宴会場として動物園を貸し出したのだが、そこに彼女がゲストとして招かれているではないか!「一緒にカー・ディーラーをやろうぜ。そうすれば彼女を取り戻せるぞ」いまだにステファニーを諦めきれないグリフィンは、そんな兄の誘いに乗って、本気で退職を考えるようになってしまう。 困ったのは動物たちだ。「あんな最高の飼育員を辞めさせるわけにはいかない。彼の仕事を辞めさせずに婚活を成功させようぜ!」 動物界のルールを破って人間語で話しかけて来た動物たちから、ワイルドな恋のアドバイスを伝授されたグリフィンはステファニーへの再アタックに挑戦するのだが……。 動物が人間の言葉を話す映画は星の数ほどあるけれど、大抵アニメっぽいキャラ。それを打ち砕いたのが、エディ・マーフィ主演の『ドクター・ドリトル』シリーズ(98〜01年)だった。同作は、当時最先端のCGを駆使して、リアルな動物が人間の言葉を喋るのを違和感なく見せて大ヒットを記録したのである。 2011年に公開された『Mr.ズーキーパーの婚活動物園』は、この手法をさらに進化させて約1億7000万ドルもの興行収益を叩き出したメガヒット・コメディだ。ディズニー製作の大ヒット作『ジャングル・ブック』(16年)は間違いなく本作の延長線上にある。 ここで『ジャングル・ブック』を連想するのは、同作の監督で俳優でもあるジョン・ファヴローが、本作でクマの声優を務めているからだ。ファヴローがあの傑作を演出できたのも、本作で色々とノウハウを得たからではないだろうか。 そのひとつが声優選び。『ジャングル・ブック』ではビル・マーレイやイドリス・エルバ、スカーレット・ヨハンソン、クリストファー・ウォーケンといった人気俳優が、声色にぴったり合う動物の声優を務めていたけど、『Mr.ズーキーパーの婚活動物園』はそれを先駆けたかのようなキャスティングが行なわれているのだ。そのメンツをざっと挙げてみよう。 まず『サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方』(91年)でゴールデングローブ賞を受賞したシリアスな俳優でありながら『48時間』(82年)では前述のエディ・マーフィと共演し、ファヴローともアニメ『森のリトル・ギャング』(06年)で動物声優として共演していたニック・ノルティがストーリーの鍵を握るゴリラ役。 アクション・ムービー界の伝説シルヴェスター・スタローンと、シンガーであり『月の輝く夜に』(87年)でアカデミー主演女優賞を獲得しているシェールという濃厚なコンビはライオンの夫婦を演じている。 『サタデー・ナイト・ライブ』出身のコメディエンヌでポール・トーマス・アンダーソンのパートナーでもあるマーヤ・ルドルフがキリン、『40歳の童貞男』(05年)や『エイミー、エイミー、エイミー! こじらせシングルライフの抜け出し方』(15年)を監督する傍ら、セス・ローゲンやジェイソン・シーゲルといった若手コメディ・スターの育ての親として知られるジャド・アパトーがゾウ、そしコメディ・レジェンド、アダム・サンドラーがサル(演じているクリスタルは、前述の『ドクター・ドリトル』をはじめ、『ナイト・ミュージアムシリーズ(06〜14年)や『ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える』(11年)『幸せへのキセキ』(11年)にも出演している名優サル!』の声を担当している。 通常、主演映画にしか出演しないサンドラーがこんな地味なポジションを務めているのは珍しい。実はこれにはワケがある。本作のプロデューサーはサンドラーで、製作会社は彼が主宰するハッピー・マジソンなのだ。そしてこれほどゴージャスな声優陣を招いてまでサンドラーがバックアップしようとした才能こそが、本作の主演俳優ケヴィン・ジェームズなのである。 ケヴィンはサンドラーと同じニューヨーク出身で、彼よりひとつ上の65年生まれ。スタンダップ・コメディアンとして活動し始め、兄貴分のレイ・ロマーノが主演したシットコム、『HEY!レイモンド』(96〜05年)への出演をきっかけに、やはりシットコム『The King of Queens』(98〜07年)の主演に抜擢。下町クイーンズで宅配業者として働く中年男役でブレイクした男だ。 本格的な映画出演は、ウィル・スミスが非モテ男に恋愛術を指南する<デートドクター>に扮したロマンティック・コメディ『最後の恋のはじめ方』(05年)から。この作品でケヴィンは、スミスの顧客となる究極の非モテ男アルバートに扮して、笑いを根こそぎかっさらうパフォーマンスを披露。スミス目当てに映画館を訪れた観客にも「あの面白いデブ、誰?」と評判を呼び、大ヒットに貢献したのだった。 その勢いで出演したのが、旧知のアダム・サンドラーとのダブル主演作『チャックとラリー おかしな偽装結婚!?』(07年)だった。ここでケヴィンは、子どもに残す年金問題に悩むあまり、サンドラー扮する結婚願望ゼロのプレイボーイと偽装同性婚をする男ヤモメの消防士を好演。すでにスーパースターだったサンドラーに負けない存在感を示した。そしてサンドラーのプロデュースのもと、遂に『モール★コップ』(09年)で単独主演を実現したのだった。 警官採用試験に挑戦しては失敗を続けているドジなショッピングモールの警備員が、モールを占拠した強盗団相手に丸腰で立ち向かうこのアクション・コメディは、ケヴィンのメタボなボディを駆使したギャグに笑わされながら、『ダイ・ハード』の流れを汲むマッチョ系アクション映画としても見れるという二刀流でメガヒットを記録した。 そしてサンドラー、クリス・ロック、デヴィッド・スペード、ロブ・シュナイダーら人気コメディ俳優が集結した同窓会コメディ『アダルトボーイズ青春白書』(10年)を経て公開されたのが本作『Mr.ズーキーパーの婚活動物園』だったというわけだ。 その後もケヴィンは、総合格闘技に挑戦する教師に扮したアクション・コメディ『闘魂先生 Mr.ネバーギブアップ』(12年)やそれぞれシリーズの続編となる『アダルトボーイズ遊遊白書』(13年)と『モール・コップ ラスベガスも俺が守る!』(15年)、そしてサンドラー主演のSFXコメディ『ピクセル』(15年、何と米国大統領役!)といったヒット作に立て続けに出演。一方で16年からテレビに逆上陸し、製作も兼ねたシットコム『Kevin Can Wait』に主演して人気を博している。つまりケヴィンはかれこれ20年以上もコメディ界の第一線に立ち続けていることになる。 同世代でこれだけコンスタントに長期間活躍しているコメディ・スターは前述のサンドラーやベン・スティラーくらいだろう。ふたりに比べると日本では知名度がだいぶ下がるけど、これはもはやコメディ・レジェンドとして扱っていいレベル。見かけはどこにでもいそうなデブだけど、実は頭が切れるスマート・ガイ、それがケヴィン・ジェームズなのだ。 そんな彼のパーソナリティに動物たちのチャームも加味された『Mr.ズーキーパーの婚活動物園』はケヴィン初心者にとって入門編にふさわしい作品だと思う。ヒロインのロザリオ・ドーソンとのコンビネーションの良さも心に残る仕上がりだ。 ZOOKEEPER, THE © 2010 ZOOKEEPER PRODUCTIONS, LLC. All Rights Reserved
-

PROGRAM/放送作品
シネマの中へ 長塚京三 映画の話
長塚京三の案内で、クラシック映画を楽しむためのポイントを予習する、ミニ解説番組
毎週土曜あさ10時の「赤坂シネマ座」。この枠で取り上げる、映画史に残る名作たちの魅力を、俳優・長塚京三さんが紹介。クラシック映画の敷居の高さを取り払う様々な予備知識で、本編が120%楽しくなる。
-

COLUMN/コラム2018.02.01
動物パニック映画の枠を超えた奇想と、驚異のミクロ描写に目が釘付けの昆虫映画2作品『燃える昆虫軍団』『フェイズⅣ 戦慄!昆虫パニック』〜2月8日(木)・9日(金)ほか
ある日突然、筆者のもとに〈シネマ解放区〉の担当さんからシュールなメールが届いた。「“昆虫セット”はいかがですか?」。要するに『燃える昆虫軍団』『フェイズⅣ 戦慄!昆虫パニック』という往年の昆虫パニック映画2本をまとめて紹介してくれという原稿の発注だ。どちらも30年以上前にテレビで観ていて、やたら面白かった記憶があるので、さして迷うこともなく「昆虫セット、承りました」と返信し、今この文章を書いている。 この2作品が世に出た1970年代は、空前のアニマル・パニック映画ブームが吹き荒れ、地球上のあらゆる動物が人類を脅かした時代だった。ヒッチコックの『鳥』がそうであったように、特に理由も示されぬままサメ、ワニ、クマなどが我も我もと凶暴化し、普段はあまり人目につかないネズミやヒルといった小動物までも人間に襲いかかった。 そんな1970年代に作られた『燃える昆虫軍団』『フェイズⅣ 戦慄!昆虫パニック』は小動物よりさらに小さい昆虫が主役であり、内容もかなりの変化球であるため、漠然とアニマル・パニック映画ブームの“後期”の作品だと思い込んでいた。ところが今回、改めてそれぞれの本編を見直すと同時に、製作年をチェックして驚いた。『燃える昆虫軍団』はスピルバーグの『ジョーズ』と同じ1975年、『フェイズⅣ 戦慄!昆虫パニック』に至ってはさらに早い1973年に作られているではないか。「そろそろブームもマンネリだから、ちょっと変わった昆虫パニックものでも作るか」といういかにも商魂旺盛なB級映画のプロデューサー的な発想とは、まったく関係なく生み出された2作品だったのだ。 まず『燃える昆虫軍団』の凄いところは、この邦題の“燃える”というのが何かの比喩でもハッタリでもなく、本当に“燃える昆虫”を描いている点だ。物語はとある夏の日、田舎町で大地震が発生し、あちこちにできた地割れから未知の虫が現れるところから始まる。その体長10センチ弱くらいの三葉虫のような生き物は、お尻のあたりにパチパチッと火花を発す特殊スキルの部位を装備しており、乾ききった草むらはもちろん、手当たり次第に車や家屋を燃やし始める。すかさずありったけの消防車が出動するが、とても消火活動は追いつかない。生物学に精通した地元の教授がこの発火昆虫を分析すると、さらなる驚きの事実が次々と明らかに。人間の足で踏みつけても殺せない屈強な甲殻を持ち、害虫の駆除薬でも死なず、草木や新聞などの燃えかすの灰を食べて栄養にするこの昆虫は、太古の時代から粘り強く地底で生き抜いてきた最古の生物だったのだ! 先ほど“三葉虫のよう”と書いたが、実際にはゴキブリを撮影に使っているので、少年時代に目の前に飛んできたゴキブリを避けようとしてガラス戸に突っ込んで大ケガしたトラウマを抱える筆者には、直視できないシーンの多い困った映画である。それでも本作から目を離せないのは、発火昆虫の意表を突いた設定に加え、アニマル・パニック映画の型にはまらない異様なストーリーが繰り広げられるせいだ。運の悪いネコや数名の人間が発火昆虫に殺害され、あちこちで火災が発生する前半はよくあるパニック映画風の滑り出しなのだが、中盤以降はパニックがスケールアップするどころか極端にスケールダウン。一軒家に閉じこもって研究に没頭していた教授が、昆虫に妻を惨殺されたことで怒りを爆発させ、彼個人の私的な復讐ドラマへ転じていくのだ。しかも何を思ったのか、太古の発火昆虫を現代に生きるゴキブリと異種交配させ、なおさら危険な新種の昆虫を創造する始末。主人公がマッドサイエンティスト化する展開に呼応して、映像のトーンもからっと明るいパニック映画から陰影を強調したサイコスリラーへと変貌していく。思わず呆気にとられつつも、その不可解なストーリーの転調をきちんとビジュアルで表現していることに感心させられる。 かくして驚異の進化を遂げ、知能も発火機能もバージョンアップした昆虫のディテールがさらに念入りに描かれ、後半にはあっと驚く“虫文字”などの見せ場が用意されているのだが、それは観てのお楽しみ。そして今回観直して気づいたことだが、日曜日に大勢の信者が集う“教会”が大地震に見舞われるシーンで幕を開け、教授が生命の創造という神をも恐れぬタブーを犯し、ついにはこの世に“地獄の裂け目”が表出する破滅的なエンディングを招き寄せてしまう構成も秀逸。すなわち本作は昆虫をモチーフにした宗教的パニック・カタストロフ映画とも解釈できるわけだ。 ちなみに手堅い演出を披露しているのは、タイムスリップSFの傑作『ある日どこかで』で知られ、今も現役で「グレイズ・アナトミー」などのTVシリーズの演出を手がけているヤノット・シュウォーク。しかし、より注目すべきは製作、脚本のウィリアム・キャッスルだろう。1950年代末から1960年代にかけて『地獄へつゞく部屋』『13ゴースト』などのホラー映画を世に送り出し、4DXの先駆けとも言えるあの手この手のアトラクション体験を観客に提供。そんな偉大なる“ギミックの帝王”がキャリアの最後に携わった一作なのだ。さすがに劇場公開時、ゴキブリを観客席にばらまくなどというシャレにならないギミックはしでかさなかったようで、本作の完成から2年後の1977年に心臓発作でこの世を去った。 うまくストレートに内容を表している『燃える昆虫軍団』に比べると、『フェイズⅣ 戦慄!昆虫パニック』はかなり損をしている題名ではなかろうか。日本では劇場未公開に終わったこの作品はチープなアニマル・パニック映画ではなく、哲学的とも言える本格志向のハードSF。遅ればせながら数年前に国内盤DVDがリリースされたことで、もはや知る人ぞ知るの域を超えて多くの映画ファンを唸らせてきたカルトムービーの逸品である。 はるか彼方の宇宙空間で発生した異変の影響が地球へと伝わり、アリゾナの小さな小さな生き物=アリの一群が奇怪な行動を見せ始める。そのアリたちは同じ種族で争うことを止めて一致団結し、カマキリやヘビといった自分たちの天敵を駆逐し、ぐんぐん勢力を拡大していく。冒頭の10分間はそうしたアリの生態がネイチャー・ドキュメンタリーさながらに超接写やハイスピード撮影を駆使して延々と描かれるので、たまたま暇つぶしでこれを観始めた人は、ザ・シネマではなく間違ってナショナル・ジオグラフィックかアニマル・プラネットにチャンネルを合わせてしまったかと錯覚することだろう。 アリたちの不思議な行動を知って現地に赴いた学者のハッブスと若いエンジニアのレスコが、シルバーのドーム状施設で研究を開始するまでが〈フェイズⅠ〉、すなわちアリと人類の存亡をかけた前代未聞の闘いの第1段階。そのドームの前には7つの幾何学的なモニュメントがそびえ立っている。人間の背丈よりもはるかに高いそのタワーは、アリたちが築き上げた巨大なアリ塚だ。学者としての情熱は人一倍だが、かなり傲慢な性格のハッブスはアリタワーを荒っぽい手段で粉砕し、上から目線でアリたちを挑発する。もともと好戦的なアリたちがその宣戦布告を受けて立ったことで、両陣営の攻防は一気に激化。虫ごときに発電機を破壊されたハッブスは、お返しに強力なイエローの殺虫液をお見舞いして無数のアリたちを抹殺する。ここからの描写が凄まじい。生き残ったアリは殺虫剤のかけらを女王蜂のもとに届けるため、決死の覚悟で運び始める。運び主のアリが絶命したら、別のアリがそれを受け継ぐという捨て身のリレー。ついに殺虫剤を受け取った女王蜂は、その薬物に耐性のあるイエローのアリを産み落とす。当然ながらCGなど存在しない時代に、本物のアリを使って“演技”させ、その組織だった連係プレーや自己犠牲をいとわない献身性を映像化してみせた撮影に舌を巻く。ましてや地下空間に戦死したアリたちの亡骸が整然と並べられた“葬儀”シーンは、揺るぎない全体主義を形成するアリ社会の圧倒的な強みをひしひしと伝え、エゴイスティックで何かと感情に左右されがちな人間との優劣を残酷なまでに浮き彫りにする。 続いて、人間が高温に弱いと見抜いたアリたちは、太陽光を反射させる鏡面機能を備えた新たなアリ塚を建造し、エアコンも破壊して(このシーンにおけるアリとカマキリとの絡みが見ものだ)、蒸し風呂状態のドームにこもったハッブスとレスコを苦しめていく。まだ〈フェイズⅡ〉だというのに、早くも人類の敗色ムードは濃厚。初見の視聴者の興趣を殺がないよう〈フェイズⅢ〉以降の詳細を書くことは避けるが、アリたちは人間をやすやすと殺したりはしない。なぜならアリ目線の一人称ショットがさりげなくも随所に挿入されるこの映画は、人類がアリを倒す話ではなく、アリが人類を観察してある目的のために有効利用しようとする恐るべき話なのだ! 監督は、ヒッチコックの『めまい』『サイコ』などのメインタイトルの作者として名高いグラフィック・デザイナーのソウル・バス。このキャリア唯一の長編監督作品で独創的な視覚的センスを遺憾なく発揮し、哲学的な寓意をはらんだ異種族間の一大戦記をヴィジュアル化した。人間の主要キャラクターは前述のハッブスとレスコ、そして研究ドームに逃げ込んできた近所の農家の娘ケンドラの3人だけ。半径数百メートルの局地戦を描きながら、『燃える昆虫軍団』よりもはるかに深遠な黙示録的なドラマを創出し、『2001年宇宙の旅』や人類と宇宙病原体とのミクロな死闘を描いた『アンドロメダ』をも連想させるレベルのSFに仕上げたその手腕には驚嘆せずにいられない。これまた男性視聴者の視覚を大いに潤すであろうケンドラ役のリン・フレデリックの麗しい魅力を生かし、アリがその柔肌を這いずり回る倒錯的なエロティシズムも表現。この紅一点の美女が単なるお色気担当ではないことが判明する衝撃的な結末にも注目されたし。 そして最後に、インセクト・シークエンス、すなわち見事な昆虫撮影を手がけたケン・ミドルハムについて。1971年にアカデミー賞ドキュメンタリー長編賞を受賞した『大自然の闘争/驚異の昆虫世界』の撮影監督であるミドルハムが、『フェイズⅣ 戦慄!昆虫パニック』で重要な役目を担っていることはもともと知っていたが、何と『燃える昆虫軍団』にもインセクト・シークエンスでクレジットされていたとは! ザ・シネマがお届けする昆虫撮影の名手によるこの2作品、いろんな意味で興味の尽きない必見&録画必須の“昆虫セット”なのである。■ TM, ® & © 2018 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.
-

PROGRAM/放送作品
シャーロットのおくりもの
命の尊さ輝く奇跡のファンタジー! ブタのウィルバーとクモのシャーロットの感動の友情物語!
23ヵ国、4500万人の読者に愛される児童文学の最高傑作を映画化! アメリカの名子役ダコタ・ファニングと動物たちの名演技に感涙必至の名作! 文部科学省選定・厚生労働省社会保障審議会推薦作品。
-

COLUMN/コラム2017.09.10
「考えるな、感じるな、ただ下らなさに笑え」香港ナンセンスコメディの正当後継映画『ドラゴン・コップス -微笑(ほほえみ)捜査線-』〜09月11日(月)ほか
おそらくほとんどの方はブルース・リーの一連の作品やジャッキー・チェンの作品のような「カンフー映画」ではなかろうか。その他にジョン・ウーの『男たちの挽歌』や『インファナル・アフェア』、ジョニー・トーの一連の作品のような「香港ノワール」を思い浮かべる方もおられるであろうし、中にはウォン・カーワイやピーター・チャンのようなアート寄りな作品を連想される方もいるのではないだろうか。 そしてそうしたジャンルと並んで、香港映画の代表的ジャンルとして今なお人気を博しているのが、コメディ映画、特にナンセンスコメディ映画なのである。 香港映画は日本の技術者の協力の下、京劇ベースの武侠映画からスタートし、キン・フーやチャン・チェのようなアクション映画に骨太な人間ドラマを持ち込んだ名監督が登場。さらにブルース・リーの登場によって、本物の武術のバックグラウンドを持つ俳優たちによる別次元のアクション映画が登場することで、最初の全盛期を迎える。ブルース・リーの急逝によってその勢いは陰りを見せるかに思えたが、ブルース・リーの遺産である「カンフー映画」というジャンルは次世代のスターを生み出せずにいた香港映画界を延命させることに成功した。 ブルース・リーによって、東アジア最大の映画会社ショウ・ブラザースと並ぶ規模に成長したゴールデン・ハーベスト社は、次なるドル箱の映画を探していた。そこで目を付けたのが、ブルース・リーと同窓で、TV番組の司会者として人気を博し、映画界に活動の場を移していたマイケル・ホイだった。 マイケル・ホイは『Mr.BOO!』シリーズ(日本の配給会社によって一連のシリーズのようなタイトルを付けられているが、それぞれが独立した作品)を立ち上げて、香港映画史上に残るメガヒットを記録。カンフーアクション映画一辺倒であった香港映画界に大きな風穴を空け、この大ヒットがジャッキー・チェン、サモ・ハン・キンポーらを輩出するコメディ・カンフー映画の呼び水になったことは言うまでもない。 『Mr.BOO!』の特徴は、言うまでもなくナンセンスギャグの連発、そして社会風刺の効いたストーリー展開だ(もちろん日本では吹替版の故・広川太一郎氏の絶大な貢献があるが、本稿では無関係なので泣く泣く割愛する)。これ以降、香港には様々な種類の映画が登場し、いよいよアジアのハリウッドとしての地位を確立していくことになる。マイケル・ホイの系譜は、さらに香港映画史上最大級のヒット作となった『悪漢探偵』シリーズに繋がり、ジャッキー・チェンやサモ・ハン・キンポーの『福星』シリーズや『霊幻道士』シリーズといったアクションコメディの大流行に繋がっていくことになる。 そして80年代後半になると、現在に至るまでヒットメーカーとして活躍する一人の天才監督が登場する。バリー・ウォン(ウォン・ジン)だ。芸能一家に育ち、テレビ局の脚本家から映画監督に転身したバリー・ウォンの名を一気に知らしめたのは、何と言っても『ゴッド・ギャンブラー』シリーズだろう。1989年にノワール食の強いギャンブルアクション映画『カジノ・レイダース』を撮りあげたバリー・ウォンは、同時期にナンセンスコメディ、エンタメ方向に思いっきり振り切ったギャンブルアクション映画『ゴッド・ギャンブラー』も制作。香港ノワールのハードコアで陰惨な世界に飽いていた香港の映画ファンは、笑って燃えて最後にホロリとさせる『ゴッド・ギャンブラー』の上映館に押し寄せたのだった。 バリー・ウォンは次々とヒット作の制作・監督・脚本を担当し、そのコメディ作品ではチョウ・ユンファやアンディ・ラウといった人気俳優の新たな側面を引き出すことに成功。そのため多くの有名スターが、こぞってバリー・ウォンの作品に出演するようになっていく。 しかしバリー・ウォンの最大の功績は、コメディ映画の次世代スーパースターを次々と発掘したことであろう。その中でも最大のスターに成長したのがチャウ・シンチーだ。チャウ・シンチーはバリー・ウォンのナンセンスコメディのあり方をさらに進化させて世界的な映画人へと成長していくことになるが、こちらも本稿とは直接関係は無いため割愛する。 さて、このバリー・ウォンの確立したナンセンス・コメディで大化けした俳優もいる。前述のチョウ・ユンファやアンディ・ラウだけでなく、『ドラゴン・コップス』の主役の一人を演じたジェット・リーだ。『少林寺』で大ブレイクした後、不遇な10年を経てコメディ要素を強くしたワイヤーアクション超大作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ』シリーズでマネーメイキングスターの地位を確立したジェット・リー(当時はリー・リンチェイ)。『ワンチャイ』シリーズの監督ツイ・ハークと揉めてシリーズを降板した後に出演したのが、バリー・ウォンの『ラスト・ヒーロー・イン・チャイナ/烈火風雲』だった。ここで『ワンチャイ』以上にワルノリしたコメディ演技を開花させたジェット・リーは次々とバリー・ウォン作品に出演。中でも今回紹介している『ドラゴン・コップス』との類似点の多い『ハイリスク』は、香港映画マニアの好事家の間でも非常に評価の高い作品だった。しかしジェット・リーはハリウッドに進出し、再びシリアス路線に戻ってコメディ演技を封印。実に8年ぶりに本格コメディ映画に復帰したのが、この『ドラゴン・コップス』なのである。 セレブリティの連続死亡事件。死体は常に微笑んでいるという怪異な事件だ。この事件を追っていた刑事プーアル(ウェン・ジャン)と相棒のフェイフォン(ジェット・リー)、そして彼らの女性上司のアンジェラ(ミシェル・チェン)は、死んだ者たちに共通点を見出す。彼らはすべて売れない映画女優のチンシュイ(リウ・シーシー)と関係していたのだった。プーアルはチンシュイから事情を聞くが、チンシュイを迎えにきた姉のイーイー(リウ・イェン)は怪しさ満開。捜査を進めていると、死んだ者たちには保険金がかけられており、その受取人はすべてイーイーだったのだ……。 映画のビジュアル的にジェット・リー主演映画のように思えるだろうが、本作の主演はプーアル刑事役のウェン・ジャンだ。テレビ俳優としてブレイクした後、ジェット・リーがアクションを封印したヒューマンドラマ『海洋天堂』で、ジェット・リーの自閉症の息子役で本格的に映画界に進出。チャウ・シンチーの『西遊記~はじまりのはじまり~』や『人魚姫』でブレイクした若手俳優だ。実生活でもジェット・リーを「パパ」と呼ぶほど仲の良いウェン・ジャンは、共演2作目となる本作でも息の合ったコメディ演技を見せており、コスプレも厭わない自信満々なポンコツという点で前述の『ハイリスク』でのジャッキー・チュンを彷彿とさせる。 またバリー・ウォンは、自作でチンミー・ヤウのような常軌を逸したような超美人女優にムチャブリを繰り返すことで有名だったが、『ドラゴン・コップス』も負けていない。台湾で大ヒットした青春ドラマ『あの頃、君を追いかけた』でブレイクしたミシェル・チェン。本作ではアクションに挑戦したり、壁に激突したりと大活躍を見せる。そして行定勲監督の『真夜中の五分前』で双子の姉妹を演じたリウ・シーシーはワイヤーアクションにも挑戦。さらにシンガーやテレビ番組の司会者として有名で、中国の美人ランキングで1位にもなったリウ・イェンは、パブリックイメージ通りの豊満なバストを半分放り出したまま登場する。 そしてジェット・リーファンなら期待するアクションも盛り沢山。オープニングではジェット・リーとの共演は『カンフー・カルト・マスター』以来6作品というコリン・チョウは、相変わらず息の合ったアクションを展開。監督・主演を務めた映画『戦狼 II』が興行収入800億円超えという世界興行収入を塗り替える大ヒットを記録しているウー・ジンも登場。そして最後には時空を超えた人物との最終決戦が待っている。 ……改めて申し上げるが、本作はハードなバディアクションものではなく、あくまでもナンセンスコメディ映画だ。真面目な作品や、コメディタッチのアクションという期待をして観るとその落差に呆然とする類の作品である。しかしあえて言いたい。 「おれ達の好きな香港映画はこれだ!」 と。 まさにマイケル・ホイが切り開き、バリー・ウォンが再構築し、チャウ・シンチーが世界を制した香港コメディ映画の正当なスタイル。本当に下らないギャグが連発し、ヒット作のパロディが随所に取り込まれ、凄まじい人数のカメオ出演者が登場するというオールスターかくし芸大会的な、香港映画が本来持っていたサービス精神の塊のような作品。その正当後継者が、この『ドラゴン・コップス -微笑捜査線-』なのだ。■ ©2013 BEIJING ENLIGHT PICTURES CO., LTD. HONG KONG PICTURES INTERNATIONAL LIMITED ALL RIGHTS RESERVED