検索結果
-

PROGRAM/放送作品
マトリックス徹底ガイド
この特番を見れば、さらに『マトリックス』シリーズの一挙放送が楽しめる!
『マトリックス』シリーズ一挙放送をより分かりやすくお届けするための、女優・川村ゆきえナビゲートによる解説番組。一度見ただけでは理解できない『マトリックス』シリーズの哲学性や深いテーマ性も、早稲田大学大学院の谷川建司教授の解説で、分かりやすく紹介していく。
-

COLUMN/コラム2018.01.30
個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2018年2月】キャロル
『007』シリーズの5代目ジェームズ・ボンドこと、ピアース・ブロスナン。イギリスを代表する俳優で、かっこいい英国紳士のイメージが強い彼ですが、今回は冷酷非情な殺し屋役でめずらしく悪役を披露。本作の制作初期段階では別の配役だったのだそうなのですが、めぐり巡って最終的にピアースがキャスティングされました。確かに、ありがちな優しいダンディ男よりも、謎多き凄腕の殺し屋のピアース・ブロスナンと言われた方が視聴意欲を喚起される気がする・・・。そしてヒロインは『バイオハザード』のミラ・ジョヴォヴィッチ。外交官で、スーツを着こなす強い女性というキャラクターに興味を持ち、出演を決めたのだとか。そういわれてみると、ジョヴォヴィッチがスーツ姿でアクションを披露するのは初めてだ。(というか、普通の人間というか現代人という役自体が初めてなんじゃなからろうか?)そんな、冷酷非情の殺し屋と、普通の人間、という普段見慣れない配役同士の二人が織り成す追及&逃亡劇は、想定している以上に新鮮です。舞台が繰り広げられるロンドンの街並みは美しく、映像に重厚感を与えていて見ごたえ十分。息をつく暇もなく次々とたたみかけるノンストップアクションを2月のザ・シネマでお楽しみください。■ © 2015 SURVIVOR PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
-
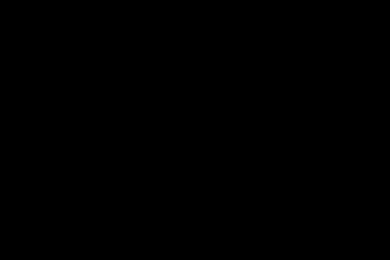
PROGRAM/放送作品
特番:映像が語る東西冷戦
東西冷戦に終わりを告げた「ベルリンの壁崩壊」、あれから20年の月日が経というとしている…
1989年11月9日、当時ベルリンを東西に隔てていた「ベルリンの壁」が崩壊。それは「東西ドイツ統一」の幕開けだった。冷戦の始まりから壁崩壊までの歴史を、時代を反映した名作映画やドキュメンタリーでふり返る。
-

COLUMN/コラム2017.12.26
2月10日(土)公開。『ぼくの名前はズッキーニ』について。
ストップモーション・アニメとは静止した粘土、紙、布などで作られた被写体をヒトコマずつ動かしながら撮影し、それが連続的に動いているように映し出す技法である。映画草創期から培われてきたこの伝統的な特殊効果の技法は、『ジュラシック・パーク』以降の実写の劇映画においてはすっかりCGに取って代わられたが、今なおその独特のアナログな動きや質感を生かしたアニメ作品が作られ続けている。世界中で愛されている『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』『ウォレスとグルミット』『チェブラーシカ』などがこの分野の代表作で、『コララインとボタンの魔女 3D』のライカ・エンタテインメント製作による『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』が話題を呼んだことも記憶に新しい。『ファンタスティックMr.FOX』でストップモーション・アニメへの偏愛ぶりを示したウェス・アンダーソン監督が、日本の架空の街を舞台にした最新作『犬ヶ島』の公開(2018年春)も楽しみだ。 アカデミー賞長編アニメ賞にノミネートされ、セザール賞、ヨーロッパ映画賞ほか数々の賞に輝いた『ぼくの名前はズッキーニ』は、スイス出身のクロード・バラス監督がフランスとの合作で完成させた長編デビュー作だ。主人公は絵を描くのが得意で、屋根裏部屋に暮らしている9歳の少年イカール。片時もビール缶を手放さない母親から“ズッキーニ”という愛称を授かった彼は、母親の不慮の死の現場に居合わせた罪悪感を引きずったまま、孤児院のフォンテーヌ園に身を寄せることになる。そこにはアラブ系やアフリカ系を含む外見も性格もさまざまな5人の少年少女がいて、のちに魔女のように恐ろしい叔母さんのもとを逃れてきた女の子カミーユも転がり込んでくる。親による育児放棄や虐待の被害者である彼らはそれぞれ残酷な事情を抱えているが、優しい園長や先生たちのもとでのびのびと毎日を過ごしている。これはそんな新たな仲間たちと心を通わせ、初めての恋も経験するズッキーニの成長物語だ。 場面写真をご覧の通り、大きな頭、まん丸の目、色とりどりの髪の毛が際立つ本作のキャラクターは、アニメならではの可愛いデフォルメが施されている。彼らはパペットと呼ばれる人形だが、ストップモーション・アニメの魔法によって命を吹き込まれ、ささいな表情の変化や仕種から豊かな感情があふれ出す。例えば、パパから性的虐待を受けたトラウマを負っている少女アリスは、ブロンド(というか、ほとんど黄色の)長い前髪でいつも顔の半分を隠しており、滅多に言葉を発しない。気持ちがテンパってしまうとフォークでテーブルを叩く癖があり、いかにも神経過敏で危なっかしい。こうしたキャラクターの悲劇性をことさら強調せず、コミカルかつキュートに、それでいて切実に表現している点にバラス監督のセンスがうかがえよう。観ているこちらが特段気にかけずとも、ズッキーニ、カミーユ、シモン、アリス、アメッド、ジュジュブ、ベアトリスという全7人の子供たちの個性が自然と伝わってくる描写の確かさに感心させられる。 過去に“心のときめきを感じた映画”として、ヌーヴェルバーグの名作『大人は判ってくれない』を挙げるバラス監督のコメントが興味深い。「現代の映画の中では、児童養護施設は虐待の場であり、自由は外にあると描かれていることが多い。『ぼくの名前はズッキーニ』ではそのパターンを反転させて、虐待は外の世界で行われ、施設は治癒と再生の場になっています」。実際、本作にはズッキーニと仲間たちが先生に連れられてスキー場に繰り出すエピソードもあるが、ストーリーの大半は孤児院の中で展開していく。自分をいじめるかもしれない悪ガキやなぜか胸が高鳴ってしまう少女との出会いは、内気なズッキーニにとってはそれ自体がささやかな冒険だ。そうした9歳の少年の心の揺らめきを丹念にすくい取ろうとしたこの映画には、アニメらしい壮大なアドベンチャーも奇想天外なファンタジーもない。登場人物はハリウッドのCGアニメのようにセリフを早口でまくし立てることもなければ、派手にせわしなく動き回ることもない。いわばリアリティに根ざした現代のおとぎ話だ。キャラクターの感情と共鳴する光と影、静寂の間合いその繊細な演出に裏打ちされた切なくも愛おしい現代のおとぎ話 ストップモーション・アニメの素朴さには観る者を童心に返らせ、ピュアな感情を喚起する作用があり、日本のわびさびにも通じる詩的な情緒がある。また、パペットをミニチュアのセットに配置して撮影を行うストップモーション・アニメは、その意味において“実写”とも言えるわけで、照明という本物の“光”と物陰に生じる“影”のコントラストに現実感がある。バラス監督はこれらの特徴を積極的に演出に取り入れ、このうえなく繊細にして多様なニュアンスに富んだ映像世界を創出している。 例えば、劇中にはセリフや音楽が途絶えた静寂の瞬間がいくつもあり、シーンが替わる直前には登場人物が風景や部屋の中にぽつんと佇んでいるだけの引きのショットがしばしば挿入される。その宙ぶらりんな沈黙の間合いはズッキーニらの内面と共鳴し、この世で独りぼっちになったような寂しさ、どこにも居場所を見つけられない不安がさりげなく表現される。スキー場ではフォンテーヌ園の7人が仲睦まじい母子の触れ合いを目の当たりにして、もともと丸い目をいっそうキョトンとさせて立ち尽くすショットがあるが、そこでの無言の“キョトン”からは憧れや喪失といった複雑な感情が読み取れる。わずか60分余りの本編にそんな胸打たれる瞬間がいくつもちりばめられたこの映画は、まさしく“多くを語らず、豊かに伝える”演出のポリシーを貫き通し、友情と初恋、他者への思いやりといったポジティブなテーマを描き上げた作品なのだ。 とりわけ秀逸なのは、母親の突然死という最悪の不幸から出発し、新たな仲間との出会いによって希望を発見していくズッキーニの心の移ろいをお天気になぞらえた演出だ。この映画は太陽の手前に雲が浮かぶ“空”のショットで始まり、同じような“空”のショットで幕を閉じるが、最初と最後ではその見え方がまったく違う印象を受ける。晴れ、曇り、雨、雷という4段階で子供たちの喜怒哀楽を表現する、フォンテーヌ園の“今日の気分予報”なるユーモラスな掲示板にも注目されたし! そして『水の中のつぼみ』『トムボーイ』のセリーヌ・シアマ監督を脚本に迎えた本作は、大人に向けた良質な児童映画であり、時折ギョッとするセリフが盛り込まれている。なかでも「みんな同じさ。誰も愛されてないんだ」などとニヒルなことをつぶやく赤毛のシモンは、新入りのズッキーニに手荒い洗礼を浴びせるトラブルメーカーだが、実は彼こそズッキーニとカミーユの初恋物語の陰に隠れたもうひとりの主人公である。この憎まれ口を連発する悪ガキは、それなのになぜフォンテーヌ園の仲間に慕われ、ボスとして君臨しているのか。その理由はラスト直前に明らかにされる。この映画には幸せな結末が用意されているが、ありきたりなハッピーエンドではない。普段は光のあたらない場所にもそっと光をあて、喜びを慎ましく、悲しみを愛おしく見つめた、とびきり深い余韻を残すエンディングがそこにある。■ 『ぼくの名前はズッキーニ』 監督:クロード・バラス脚本:セリーヌ・シアマ原作:ジル・パリス「ぼくの名前はズッキーニ」(DU BOOKS刊) 原案:ジェルマーノ・ズッロ、クロード・バラス、モルガン・ナヴァロアニメーション監督:キム・ククレール 人形制作:グレゴリー・ボサール音楽:ソフィー・ハンガースイス・フランス/2016年/カラー/66分/ヴィスタサイズ/5.1ch/フランス語/原題:Ma vie de courgette/日本語字幕:寺尾次郎後援:スイス大使館、在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本配給:ビターズ・エンド、ミラクルヴォイス宣伝:ミラクルヴォイス 公式サイトはこちら©RITA PRODUCTIONS / BLUE SPIRIT PRODUCTIONS / GEBEKA FILMS / KNM / RTS SSR / FRANCE 3 CINEMA / RHONES-ALPES CINEMA / HELIUM FILMS / 2016
-

PROGRAM/放送作品
シネマ・トーク ~映画雑誌編集長スペシャル2009~
日本を代表する映画雑誌の編集長が繰り広げる夢の豪華座談会が今年も開催!
洋画専門CS放送ザ・シネマでは、昨年末に放送し大好評をいただいた、日本を代表する映画雑誌の編集長が繰り広げる“夢の豪華座談会”を、今年もお届けします!映画雑誌編集長ならではの熱いトークを是非ご期待ください!
-

COLUMN/コラム2017.10.29
個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年11月】キャロル
『ワイルド・スピード』シリーズのポール・ウォーカーと、女優・企業家・3児の母としてスポットライトを浴び続けるジェシカ・アルバ共演の、もはや夏の定番ともいえる『イントゥ・ザ・ブルー』。今や“豪華”共演ともいえる夏休み感満載の映画を、秋真っ盛りの11月に放送します!(公開も秋だったモンネ)監督のジョン・ストックウェルは、『クリスティーン(1983)』で注目され、トム・クルーズと『トップガン(1986)』含め二度共演を果たすなど、もともとは俳優としてキャリアを積んでいた人物。やがて脚本家・監督としての才能も発揮し、サーフィン大会を目指す女子を描いた青春映画『ブルー・クラッシュ(2002)』でブレイク。本作『イントゥ・ザ・ブルー(2005)』を続けて大ヒットさせます。この2本のヒットでマリン系が得意なイメージが定着しました。そんなわけで本作は、海の底には莫大な財宝が眠っている・・・という海洋ロマンを描いたアクション・サスペンスです。が・・・!見どころは唯一、ジェシカ・アルバのプリップリボディにあり。と言い切っても良いかもしれません!!ジェシカは、ティーネイジャーの頃にテレビシリーズ『ダーク・エンジェル(2000)』で大ブレイク。30代の今もその輝きは衰えることなく、女優という職業を超え、ファッションアイコンとして、そして年商180億の企業家として、さらに3児の母として、ハリウッドセレブでありながら地に足の着いた等身大の姿が、世界中の女性たちから絶大な支持を得ています。パッチンパッチンにはじけるボディで一時期はセックスシンボルとも称されましたが、実は敬虔なカトリック教徒でも有名(後にセックスシンボルの扱いに”very uncomfortable”であったと告白している)。ピュアな信仰心が全身から滲み出ているからかどうなのか、はじけるボディの水着姿がもはや神々しいというかスピリチュアルというか、なぜかイヤらしくないという不思議!スキューバダイビングのライセンスも取得しているだけあって、泳ぎのシーンも美しい。是非堪能してください。さいごに、主演のポール・ウォーカー。『ワイルド・スピード』シリーズで一躍スダーダムを駆け上がった彼は、人気絶頂の時期に本作『イントゥ・ザ・ブルー』に出演。昨年11月30日、『ワイルド・スピード』第7作目の撮影期間中、チャリティイベントの帰路で交通事故に遭い、40歳という若さで惜しくもこの世を去りました。一回忌に合わせて、11月30日に、ザ・シネマでは主演作『イントゥ・ザ・ブルー』を放送します!どうぞお楽しみに。■ ©2005 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved
-

PROGRAM/放送作品
シャーロットのおくりもの
命の尊さ輝く奇跡のファンタジー! ブタのウィルバーとクモのシャーロットの感動の友情物語!
23ヵ国、4500万人の読者に愛される児童文学の最高傑作を映画化! アメリカの名子役ダコタ・ファニングと動物たちの名演技に感涙必至の名作! 文部科学省選定・厚生労働省社会保障審議会推薦作品。
-

COLUMN/コラム2017.10.26
『イン・アメリカ/三つの小さな願いごと』に出てくるアイルランド料理「コルキャノン」のレシピに挑む!!!
写真/studio louise 10月23日、選挙明けの月曜日。通勤時間帯に台風直撃につき会社を休んだため急遽時間ができましたので、ズル休みと言われたくないから仕事しよ。『イン・アメリカ/三つの小さな願いごと』に登場する「コルキャノン」というアイルランド料理を作ってみました。れっきとしたお仕事でしょ?ちょっと前回のプッタネスカからあまり間が空いてませんが連投ご容赦を。書くなら書くで少々急ぎたい理由がございまして。10月31日までにアップしないと時宜を逸する。 まず映画紹介から。幼い息子を亡くしたジョニーとサラの夫婦は心機一転、娘のクリスティとアリエル2人を連れてアイルランドからニューヨークに移住する。古アパートで新生活を始めるが貧しさに苦しみ、また息子の死の哀しみから抜け出せず、夫婦の間にはすれ違いが生じていた。それでも娘たちは、何もかも新鮮な毎日に幸せを見出していく。そんなある日、幼い娘たちはアパートの不気味な隣人マテオと知り合い、絆を深めていくが…。 監督のジム・シェリダン自身がダブリン出身のアイルランド人で、半自伝的な作品とのこと。39℃のうだるような夏にマンハッタンに越してきて、秋、冬、と、過ぎ行く季節の中で末っ子を失った傷を癒し再生していく家族の物語が綴られます。家族の閉じた関係への闖入者として、ご近所さんのアフリカ人(アフリカ系ではなく本物のアフリカ人)画家マテオが関わってくる。 演じるのはジャイモン・フンスー。恐モテですよね。本作でも、マンションのドアに「入って来るな!」とペンキで大書したり独り暮らしの自室で大声を発し意味不明なことを叫んだりと、超恐い。集合住宅でドアに怪文書みたいなの貼ってたり支離滅裂なことわめき散らしてる隣人がいる、って、それは超恐い!そして、よくある話だ!! けど知り合ってみると意外と良い奴だとわかり、食事に招待するのですが、それはちょっと緊張感をともないます。その日はハロウィンです。日本人にも今やすっかりお馴染み「トリック・オア・トリート!」で娘たちがマテオのドアをノックしてしまい、それキッカケでそういう成り行きになったのです。 そのハロウィンの食卓でふるまわれるのが、「コルキャノン」という料理。ちょっと、見た目がベチャベチャしててあまり美味そうには見えなかったなぁ、この映画を初見で見た時には。マテオも引きます。「こりゃ何だ!?」と。 小さい方の女の子が「コルキャノン」と教え、お姉ちゃんが「ジャガ芋とキャベツよ」と説明する。ただ、英語のセリフだと、It's potatoes mixed with curly kale. と言っていて、具材が違う!キャベツなのかケールなのかどっちなんだ!と思いますが、気になってレシピをあれこれ調べてみますと、どっちも正解。どっちも使う(またはどっちか一方でもいい)とわかりました。 で、この映画を最初に見てすぐに気になって作って食べたのですが、一言で言うと、マッシュポテトにケールかキャベツか両方かは知りませんが緑の野菜がただ入っただけのもの、です!別にベチャベチャはしていません。 監督はあまり食い物を撮ることに関心がないのかな?食い物のシーンでは作家性が出ますな。当企画でも、『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』は“飯テロ”なんて言われるぐらいに超美味そうに撮ってましたが、『レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語』は皿をほぼ映しもしませんでしたしね。まったく食に関心がない監督なのでしょう。本作は、関心がないのか、それとも意図的にマテオ視点で“付き合いのないご家庭にお呼ばれして得体の知れない食い物を出された”という緊張感を演出したいのか断定できませんが、少なくとも美味そうには撮ってない。 でも、実際に食べると、地味に美味かったですよ。全然なにかの付け合せとしては“有り”です。ただ、とにかくマッシュポテトに毛の生えたようなものなので、これだけをワン&オンリーなメインディッシュとして食べることは不可能だと、最初に作った時に思い知りました。飽きる!これはあくまで付け合せです。 ということで学習しました!今回は簡単な肉料理もついでに作ってみました。そちらは映画には出てこないので詳しく書きませんが、別に何でもいいと思います!よく見ると劇中でも肉らしい一皿が別にありますな。とにかく、コルキャノン1品だけってのはオススメできません。 さてと、前置きはこれくらいにして早速いってみましょう!本場アイルランドではハロウィンの定番メニューというこのコルキャノン。作るとしたら今ですよ!? 【材料(2人分)】 ・キャベツ×半玉 ※外葉3枚は肉料理に流用 ・牛乳×250ml ※肉料理にも使う ・バター×適量 ・リーク×1本(無ければ長ネギで代用) ・生クリーム×1パックの半分 ※残り半分は肉料理に流用 ・ケール×数枚 ・男爵いも2個×人数分 【作り方】 ① 鍋にジャガイモを入れ水をヒタヒタに。沸騰させ、ほとんど水が蒸発し残り1~2cmになるまで沸かし続ける。これは時間がかかるので、②、③の作業を進めておく。 ② キャベツ半玉、では多すぎるので外葉3枚ほどはむしって取っておき、残った中心部を適当な大きさに切る(軸は捨てる)。ケールも適当な大きさに切る。フライパンでしんなりするまで熱を入れ(油は不要。焦げそうなら水を少量足して)、しんなりしてきたらリーク(長ネギ)小口切りを最後に投入し、ラスト2分ほど加熱。最初からネギを入れて加熱するとネギっ臭さが飛んで風味が失われてしまうため。 ③ フライパンの中身②をフードプロセッサーにかける。 ④ ジャガイモが茹で上がったら鍋から出し、いったん鍋を空にし水を切り、ポテトマッシャーでマッシュポテト状にしたものを再び鍋へ。最後に加熱し、ベチョベチョになりすぎないよう水気を飛ばす。 ⑤ ④の上に③、その上にバター、塩、コショウすべてお好みの量を。 ⑥ 生クリーム半パック、牛乳1/2パックのさらに半分(250ml)を注ぎ入れ、バターが溶けるまで加熱しながら混ぜる。ボソボソすぎる場合はさらに若干の牛乳を追加して滑らかに整える。 完成!ただ、これだけだと飽きるということで、今回はプラスもう1品。「ベーコン&キャベツ」という、これまたアイルランドの伝統料理もあわせてご紹介。ただしこちらは映画に登場しないので、レシピも一言で短く済ませる。ブロックベーコン1本を香味野菜(タマネギ×1個、ニンジン×1本、セロリ×1本、ローリエの葉1枚)と一緒の鍋に入れ、水をヒタヒタにして30分煮込む。途中で前述の②で残ったキャベツの外葉3枚も入れ、クッタリしたら引き上げ水気を切り大皿に敷き詰める(キャベツは煮込みすぎ禁物。とろろ昆布みたいに解けちゃうので)。30分たったらブロックベーコンを引き上げ冷めるまで待ち、冷めたら極力薄くスライスし、大皿の上のキャベツの上に並べる。香味野菜は香り付けなので、捨てるの勿体無かったら自由なスープの具にでもして食べちゃってOK。一言じゃムリだった!二言で。ソースも作る。ソースパンで⑥で残った生クリーム半分を加熱し塩コショウ。フードプロセッサーでみじん切りにしたパセリも投入し、パセリソースを作る。ドロドロ状に煮込むがドロドロになりすぎた場合は⑥の牛乳の残りで薄めて、程よい状態に整えたら、大皿の上のキャベツの上にかけ流す。以上! 【実食】 いや~、素朴でうまいっすねー!いろどりも緑で、緑ってのはアイルランドのシンボル・カラーなのです。あと、ジャガイモはアイルランドの名物食材で、ヨーロッパで日本人好みの男爵イモ系ホクホク食感のジャガイモを好むのはアイルランド人だけだと言われております。アイルランド料理のいいところは、素朴な味わいにありますね。ニンニクもあまり使わないぐらいで塩味ベースで。ただ、コルキャノンだけでは飽きるので(本来は付け合せですからね)、ガッツリ肉も必要です。今回はベーコン&キャベツで。ご飯とおかずみたくコンビで食します。 あと言うまでも無く、こりゃギネスが合う味ですな!当然、それを食べる用に土地の酒というのは発達してきましたから、合わないワケがない!超イメージだけで言いますと、ホッコリ素朴なアイルランド料理は、冬こそ似合う。映画と無関係なので紹介しませんが、ダブリン・コドルとか、あと、もしマトン肉が売ってたらアイリッシュ・シチューというそのものズバリな名前の料理とかを作ってみるのもオススメします。特に冬場には!この2つはジャガイモをゴロゴロ使ったアイルランド版の鍋物ですが、煮込めば部屋ごと温まる、これからの季節にぴったりのメニューです。 [余談ながら] ハロウィンはもともとアイルランドの風習だったのです。これについては、アイルランドのアニメ『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』で監督インタビューした際、ガッツリ監督と語り合ったことがありますので、そのリンクも載せておきましょう。ハロウィンとは何ぞや!? この機会にお読みいただければ幸い。 © 2003 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
-

PROGRAM/放送作品
スパイ・ゲーム
ロバート・レッドフォードとブラッド・ピットの初共演で話題となったサスペンス・スパイ・アクション!
窮地に陥ったかつての弟子を救おうとするCIAエージェントをロバート・レッドフォードが演じ、彼が監督した『リバー・ランズ・スルー・イット』で彼の再来といわれたブラッド・ピットと初共演した話題作。
-

COLUMN/コラム2016.07.29
『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』公開~「このへんなようせいさんたちは、まだアイルランドにいるのです。たぶん。」~監督インタビューで迫る、「どうして“ポスト・ジブリ”と評されているのか!?」の謎
『オブ・ザ・シー 海のうた』は、日本ではまだあまり知られてはいないアイルランドのアニメーション監督の第2作だ。劇場長編デビュー作である前作は日本未公開。それでもこの監督とその最新作には、今回、日本人なら誰もが注目しておかなければならない。理由は、監督トム・ムーアと彼が創設したアニメ制作会社カートゥーン・サルーンが“ポスト・スタジオジブリ”と評されているからだ。その評判が本物だということは、2作しかない監督作がどちらもアカデミー長編アニメ映画賞にノミネートされていることで証明できる。 宮崎駿は引退した。一方のハリウッド勢、ピクサー&ディズニー、対するドリームワークスのアニメはここ十何年間か、実写も及ばないような映画の質的高みに昇りつめており、ユニバーサルもソニーも負けておらず、1作ごとに驚かされ泣かされている。だがいずれも宮さんが抜けた穴を埋めるような活躍ではない。たしかに素晴らしい傑作が矢継ぎ早に送り出されてはいるが、宮崎アニメの魅力は、それとは全く別のものだったからだ。 だがついに、ポスト宮崎駿が西の果てアイルランドから出現したというのである。それほどの監督のデビュー作が未公開で、2作目にしてようやく、字幕だけでなく吹き替えでも公開されると決まったというのだから、これは観ないわけにはいかない! 監督にインタビューするチャンスを得て、この機会に一日本人観客として迫りたかったのは、「何がどう“ポスト・ジブリ”なのか!?」という点だ。だが、そのインタビューに入る前に、まず今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』のあらすじを紹介しておこう。 【ストーリー】海辺の灯台の家で、幼いベンはお父さんお母さんと暮らしていました。ベンは大好きなお母さんから「あなたは世界一のお兄ちゃんになるわ」と褒められて、赤ちゃんが産まれてくるその日を楽しみにしていました。優しくて物知りなお母さんはベンにたくさんのお話や歌を教えてくれます。巨人のマクリルと愛犬の物語や、アザラシの妖精セルキーが歌うと妖精が家に戻れる不思議な伝説、古い言葉で綴られる美しい歌など……。 ある晩、ベンはお母さんに海の歌が聞こえる貝の笛をもらいました。うれしくて、笛を大事に抱いて眠りについたのでしたが、目を覚ますとお母さんの姿がありません! お母さんは赤ちゃんを残して、海へ消えたのです。それから今も、ベンとお父さんの心は傷ついたまま。お母さんがいなくなったのは妹・シアーシャのせいだと思っているベンは、ついつい彼女に意地悪をしてしまうのでした。 6年がすぎて、今日はお母さんの命日でもある、シアーシャの誕生日。町からお祝いにやってきたおばあちゃんは、いまだに喋らない彼女が心配でたまらないようです。その夜、シアーシャは美しく不思議な光に導かれ、お父さんが隠していたセルキーのコートを見つけ、海へ入ってしまいました。悲劇の再来を恐れたお父さんはコートを海へ投げ捨ててしまい、おばあちゃんは嫌がる兄妹を町へ連れて行くのでした。町はハロウィンでお祭り騒ぎ。居心地の悪いおばあちゃんの家から抜け出した兄妹は、愛犬クーとお父さんが待つ家へ向かいます。そんなふたりの後を妖精・ディーナシーの3人組が追いかけます。彼らはシアーシャがセルキーだと気づき、フクロウ魔女のマカとその手下のフクロウたちのせいで石にされた妖精を元通りにしてほしいと頼んできたのです。その時、4羽のフクロウがシアーシャに襲いかかり、ディーナシーたちの感情を吸い取って石に変えてしまいました。その場は逃げ切ったふたりでしたが、ベンが目を離した隙にシアーシャがいなくなってしまいました。妹を探すうちにベンは語り部の精霊・シャナキーから、マカの歪んだ愛情が妖精の国と妹の命を消しつつあると教えられます。マカの魔力に勝てるのはセルキーの歌だけ。それもハロウィンの夜が明けるまでに歌わないと、すべてが消えるというのです。ベンは、妹と妖精たちを救えるのでしょうか!? 今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』、映像がとにかく美しい。絵本が動いているような絵は、写実的なジブリというよりむしろ、デフォルメされた可愛いキャラデザととことんデザイン化された美術から、『まんが日本昔ばなし』とつい世代的にはたとえたくなってしまう。ケルト音楽バンドのKiLAによる音楽が、この絵本調の映像世界をよりいっそうフォークロリックに引き立てる。 「ジブリっぽい」というのは、そうした見た目上の表面的な部分ではなく、もっと深い、作品の魂の部分をさして言っているように個人的には感じられたが、そのことにはおいおい触れるとして、まずは監督に直接お礼を伝えたい。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 聞手:本当に美しかったです!ありがとうございました。映画を観てこんなに「きれい!」と思えたのは何年かぶりです。今回、今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』と、デビュー作『ブレンダンとケルズの秘密』も拝見しましたが、有名な絵画へのオマージュを幾つか発見したような気がしています。パウル・クレーとかクリムトとか。当たっていますか? 監督:全くその通り!当たってます。 聞手:クリムトっぽいと感じたのは、今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』にも前作にも美術の中に多用されている、渦巻き模様を見た時です。渦巻きのクルクルっと蔓が伸びるような動きを見ていてそう感じたのですが、あそこまで渦巻きにこだわって、繰り返し何度も何度も描いているのは、いったいどういう理由からなのでしょう? 監督:渦巻きや螺旋、それに幾つか重ねた円。それらはケルト人に先立つ太古の時代のピクト人*01たちが遺した装飾なのです。ピクト文化というのは、アイルランドやスコットランドに大昔あった石の文化ですね。 私の映画ではイメージ作りのため、そうした古代のデザインを取り入れています。大昔の文化と現代の芸術をつなぐということは、この映画で達成しようとしている試みにとって大変に重要でして、劇中、神話や民話のキャラクターと人間のキャラクター、2人の異なるキャラクターを、そっくりの顔に描いたり声優にも1人2役やってもらっていたり、リンクさせているのですが、それも同じ狙いからです。 この映画は、古い民話の中に私たちの芸術を見出すことはできるか?私たちの真実を民話の中に見つけることはできるか?そこにチャレンジしようとしています。古い民話を現代の観客のために描き直す、解釈し直す、ということに挑みたかったのです。 *01…今のイギリスのスコットランド辺りにいた先住民族。アイルランド人やスコットランド人、ウェールズ人の祖でもあるケルト民族の一派ともされるが、言語系統が不明で、ケルト系ではない可能性もあり、謎が多い。 そういうわけで、ピクト人が遺した様々なイメージ、石に刻まれた模様などを、アートディレクターのエイドリアン・ミリガウに見せた時です。彼が「これはパウル・クレーやカンディンスキーだ!」と言った。それらの現代美術も古代のデザインから引用していたんですね。 聞手:古代のデザインを現代美術の巨匠たちが引用し、その絵画と、そもそもの古代のデザインを、あなたは作品にさらに引用して、古代と現代をつなげる、ということを試みているわけですね。しかし、なぜ古代と現代をつなぐことがあなたにとってそこまで重要なのですか? 監督:アイルランドでは95年から07年まで「ケルトの虎」と呼ばれる高度成長期があったのですが、その時に不安を覚えたからです。昔ながらの風景を残さず、その上に舗装道路を作ろうとしたりショッピングモールを建てようとしたり。社会の表層、上の層が塗り変えられていくのと同時に、その下の層にある、いにしえの文化までもが忘れ去られようとしている。そのことに危機感を募らせたのです。 聞手:東京も同じですね。日本で高度成長というと戦後の1960年代だったのですが、我々日本人は、監督の仰る“下のレイヤー”まで東京をメチャクチャに掘り返してしまって、もう原状回復はとても無理そうです。江戸の町を思わせる遺構も文化も今ではほとんど残っておらず、残念でなりません。ダブリンはどうでしょう?原状回復できそうですか?もう手遅れですか? 監督:私は、ダブリンの中心街のどこにでも、古い時代の遺跡やその名残りみたいなものが今でも残っていると感じますね。ところで、自分はとてもラッキーだったと思っているのですが、私はキャリアの中で2つの時代を経験しているんですよ。お金はいっぱいあるけれども価値観がなかなか思う方向に行かない時代と、あまり経済は良くないけれども、その中でも芸術を大事にしていこうという時代です。まず、スタジオを99年に設立したので、当時は好景気でしたから政府の助成を受けながら映画作りを始めることができました。 やがて08年にバブルが崩壊すると、今度は、経済が危機的状況でも芸術は大切なのか?という課題に取り組むことになったのです。「ケルトの虎」が崩壊したこの経済危機の時にアイルランドが直面したのは、物質文明から脱却するにはどうしたらいいのか、という大きな課題でした。この時に人々の考え方は大きく変わりましたね。失いかけていたものを思い出し、それを大切にしようと考えるようになった。幸か不幸かアイルランドの経済成長期は先進国の中でも遅くやってきた方なので、古いライフスタイルを守っていったり蘇らせたりできる選択肢が、その時点でも私たちには残されていたのです。 しかし、一方で私は、古くからの文化というものは消そうと思ったってそう簡単に消え去るものではないとも思っていますが。私たちの世界観の中にあまりにも深く、物の見方として根付いてしまっているからです。例えば音楽ですね。 聞手:今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』の音楽を担当しているKiLAのケルティッシュ・サウンドがまさにそれですね。日本では何年か前に「トイレの神様」という曲が流行ったのですが、おばあちゃんの訓えで「トイレには神様がいるからいつも清潔にしておきなさい」といった歌でした。日本には八百万の神がいると言われています。トイレにまでいる。田舎に行くと道路脇に『千と千尋の神隠し』の冒頭に出てきたような石の祠や道祖神が、今でもそこらじゅうに建っています。宗教として信仰しているというほどのことはなくても、たとえばその祠を蹴り倒したりするのは、とても罪悪感を覚える、バチが当たったって不思議はない、と、ちょっと畏怖する程度には今でも誰もが信じています。 アイルランドではどうなのでしょう?今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』も民話の妖精たちがたくさん出てくる物語ですし、日本でも“妖精の国アイルランド”といったイメージを、貴国や欧米文化に少し詳しい人ならば抱いていますけれども、そうしたイメージ通りなのでしょうか? 監督:私の祖母の世代はトゥアハ・デ・ダナーン(Tuatha Dé Danann)*02やディーナ・シー(daoine sídhe)*03の存在を本気で信じていましたね。カトリックを信じるのと同時に妖精の存在も100%信じていて、教会に行くかたわら妖精にもお供え物をしていた。その信仰はアニミズム*04的な色合いが濃くて、自然や大地への尊敬、あるいは畏怖というものを祖母たちは持っていました。 *02…アイルランド・ケルト神話に出てくる神族。現在アイルランドに暮らす人間のケルト民族との戦いに敗れたこの神々は、塚の奥底深くや海の彼方へと逃れ隠れて暮らすようになり、キリスト教が伝来してからは体も小さく縮んで妖精(sídhe)に落魄してしまった。*03…02の神々のなれのはての妖精(sídhe)のこと。今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』にも、主人公兄妹を不思議な冒険に導くキーキャラクターとして、3人の老ディーナ・シーが登場する。*04…「精霊信仰」のこと。原始宗教の特徴とされる。例えば日本の“山の神”、“川の神”、“滝や奇岩を御神体として拝む”、“古道具に魂が宿る”といった信仰は典型的なアニミズム。 今、アイルランドもまるでアメリカの一角みたいな風景に変わりつつある中で、祖母たちのような時代は永遠に過ぎ去ろうとしている。ですが、例えば先ほどあなたが言っていた流行歌とか、そういった形でもいいので、新しい信仰の形、文字通りの信仰ではないし呪術的なものでもないけれど、そうした新しい信仰のあり方を通して、アニミズムへの思いや“何かを尊重する”ということを、現代の世代は受け入れ、引き継いでいけるのではないかと考えています。 アイルランドにエディ・レニハンという現代のシャナキー(Seanchaí)*05がいるのですが、彼が「フェアリー・ツリー」と呼ばれている1本の樹を守る運動をしていたことがありました。自分の体を樹にくくりつけ、樹を倒して道路を作ろうとしている人たちに抵抗したのです。その運動のおかげで樹は倒されず道路が樹の周りを二手に迂回して作られることになったのですが、ある時私は彼に「その樹が本当に妖精の樹だと信じていたのか?」と聞いてみたことがあるんです。すると「いや、そうは言わない。だが私にこの樹の言い伝えを聞かせてくれた人は確かにそう信じていた。樹を守る理由としてはそれで十分じゃないか」と言うのです。妖精を信じる/信じないではなく“何かを尊重する”という態度の問題なのだと私は考えています。 *05…アイルランド・ケルト人の語り部のこと。古代、ケルト人は氏族の歴史と掟を明文化せず、それらを語り部の暗唱に頼った。したがってシャナキーは氏族社会において尊敬された。現代においてはアイルランドの口承文学・伝統芸能とみなされている。 聞手:私事で恐縮ですが、うちの近所に敷地が凹型の家がありまして、へこんだところには『となりのトトロ』に出てくるような大樹が生えており、おそらく御神木か何かで切れなかったんだろうと思うのです。貴国と日本は考え方が似ていますね。今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』に出てくるセルキーの伝説も、もともとは、アザラシは毛皮を脱ぐと中身が美女で、毛皮を人間の男に隠され結婚させられるが、何年かして毛皮を見つけ出してアザラシに戻り、子供を残して海へと帰ってしまうという話だと本で読みました。これも、日本の天女の羽衣伝説にあまりにもソックリで、ビックリしています。ところで、今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』で主人公兄妹を引き取って都会に連れて行く、ちょっと偏屈そうなおばあちゃん。家中にキリストの聖画とか十字架とかを掛けていましたが、あのキャラクターだけとても宗教色強く描いている意図は? 監督:特にそういう意図では描いていません。むしろ、カトリックがアイルランド中で広く信仰されていると描こうとしていますよ。例えば、子供たちがバス停でバスに乗り込むシーンでは、あれは停留所が教会の前だったでしょう。そしてバスを降りたところから歩くと聖なる泉にたどり着きますが、そこの祠にはマリア様の像がたくさん飾られている。歴史的には聖母信仰やキリスト教は、その前のアニミズムの様々な女神たちの信仰に覆いかぶさるようにして信じられていったのです。この映画の中でも、聖なる泉の祠のシーンでは、入るとすぐにキリスト教の文化があって、そこから先、奥へ奥へ、地下へと降りていくと、深い所は偶像崇拝の異教的な世界が広がっており、そこを主人公は進んでいくことになるわけです。 聞手:2つの宗教や異文化が混ざり合う「シンクレティズム」ですね。日本でも、例の八百万の神というのを信じるアニミズム的な土着の神道と、外来の仏教という2つの宗教があって、その2つは歴史的に「神仏習合」とか「本地垂迹」とかいった混淆現象をよく起こしています。 監督:面白いですねえ。ちなみにアイルランドには聖人崇拝があります。全員キリスト教の聖人ということになってはいますが、もともとはケルトの神々だったのです。昔の神の性格を引き継ぎながらも、キリスト教の聖人として新たにフィクションとして作られたのではないかと私は考えています。あと、アイルランドと言えばセント・パトリックス・デーが有名でしょう?シンボルマークが三ッ葉のクローバーで、それはキリスト教の三位一体に由来すると一般的には信じられていますが、もっともっと古い時代の名残りではないかという説もあるのです。聖パトリック*06以前から、先史時代から、アイルランドには三位一体信仰があって、3人の女神を信仰していたとも言われているのです。私の考えでは、ある宗教が入ってきて何かを乗っ取ってしまうのではなく、土着の信仰と融合して現地化していく信仰のあり方が一番うまくいくと思います。 *06…アイルランドにキリスト教を布教したとされる聖人。その命日がセント・パトリックス・デーで、本国のみならずアメリカなどでもアイルランド系移民(および全然関係のない異民族異人種)によって祝われ、映画の中でもしばしば描かれる。 聞手:今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』で物語のメインとなるのはハロウィンの1日ですが、ハロウィンも、土着の古代ケルトの祭りが後に外来のキリスト教と混じり合ったシンクレティズムの顕著な例ですね。 監督:その通りです。ハロウィンはケルトの言葉では「サウィン(Samhain)」と呼ばれていましたが、ケルト暦では1年間でもっとも重要な日だとされていました。現実世界とそうでない世界、この2つの世界を隔てる壁がとても薄くなる日です。ディーナ・シーたちがそのままの姿で歩き回っても怪しまれない日なんてハロウィンだけです。ヒントを得たのは『E.T.』です。ほら、思い出してみてください、あの映画でも子供たちがETを連れて外に出るのはハロウィンだったでしょう?あと個人的な話ですが、忘れもしない87年の出来事で、当時私は10歳でしたけれど、ハロウィンの晩に大嵐が来たことがあって、私と妹はとても怖がったのですが、そんな時、母が「この風はシェイダン・シー(séideán-sídhe)という、妖精が家に帰る時に吹く風なんだよ」と教えてくれました。あのシーンは『E.T.』だけでなくそんな子供時代の思い出からも着想を得ているんです。今作のクライマックスには、主人公たちが家に無事たどり着けるように先導してくれる2頭の犬の精霊が出てきますが、あの犬は風が形をとっているという設定です。なので、駆け抜けていくところを、つむじ風として表現していて、民家の戸板を吹き飛ばしたりする。風とハロウィンが結びついているのは、極めて個人的な私自身の思い出から来ているんですよ」 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』(と前作)を見て、インタビューも終えた今、大いなる疑問であった、この監督と彼の制作会社の「何がどう“ポスト・ジブリ”なのか!?」が解ったような気がする。 ジブリ、というか宮崎駿は、主に『となりのトトロ』、『もののけ姫』、『千と千尋の神隠し』の3作品で、埼玉の鎮守の杜にそびえるクスノキの大樹や、粗大ゴミが不法投棄される川に今も神はいて、さかのぼって(と言ってもたかだか500年ほど前の)戦国時代の深い森には荒ぶる神々がおり、森を切り開く人間どもと生存競争をくりひろげていた、ということを描き、20世紀を生きていた当時の我々に見せつけた。そうやって日本のあまねく一般大衆に、日本はアニミズム息づく神の国なのだという事実を再発見させたのである。この世ならざる巨木や奇岩の前に立つ時、条件反射的かつ生理的に畏怖の念を覚え、それに神性すら認めてしまう我々としては、大いに納得がいったものだった。あの感覚を実感として生々しく感じた覚えのある我々日本人の前に、宮崎アニメは民俗学的説得力、宗教社会学的リアリティをもって提示され、この国には、目にはさやかに見えねども、八百万の神がいるのだと、あらためて信じさせてくれたのである。「このへんないきものは、まだ日本にいるのです。たぶん。」とはよく言ったものだ。だがいつか、マックロクロスケことススワタリのように(彼らもまた言うまでもなく神様だ)居づらくなったからとコッソリ出て行かれたりしないよう、我々日本人はこれからも、トトロ神やニギハヤミコハクヌシにお供え物を絶やさず、その神域をいつも清め(トイレの神様にそうするように)、お祀りしなければならないのである。 続いては、世界がニッポンを再発見する番だった。一方で仏教といういわゆる“高等”宗教(または普遍宗教)を持ちながら、あわせて、このような古代からの宗教観(いわゆる“原始”宗教または民族宗教)も持っている日本人。それが、その精神構造のままで、当時世界第2位の経済大国にまで昇りおおせている。最先端のテクノロジーを使い倒している。その現実の、途方とてつもないギャップたるや!ファミコンを作り『AKIRA』を作り半導体を作り低燃費高性能な自動車を作りながら、同時に、クスノキの神や川の神を信じてもいる日本民族。宮崎アニメは世界にその超絶ギャップも再発見させ、激しくギャップ萌えさせたのだった。なんと摩訶不思議な民族なのだろう、日本人という連中は! トム・ムーア監督とカートゥーン・サルーン社の作品を観ると、あの当時と同じ発見がある、驚きが蘇る、ということなのだろう。確かに“ポスト・スタジオジブリ”である。ジブリに、とりわけ宮崎アニメに、なかんずく『トトロ』、『もののけ』、『千と千尋』の3本の偉大さに、極めて近いところまで迫っている、と強く感じさせる魅力がある。 カトリックという普遍宗教を奉じながら、太古の神々のなれのはてである妖精たちの存在を今なお心のどこかで信じているアイルランドの人々。そんな精神風土の過去と現在をつないで作品に描くアニメ作家の出現に、世界は再び驚嘆し、映画的な幸福をかみしめながら次作を待望している。「ヨーロッパ文明の一角に、しかも西欧圏に、原始アニミズムを信じる民族がいた!」 かつてイエイツらによるケルト復興運動によって19世紀に一度は再発見されたその魅力も、リバイバルから百年以上が経過して推進力が落ちつつあった。いま三たび、世界は不思議の国アイルランドを驚きをもって発見したのである。 その驚きと、豊かで自由なアイルランドの精神風土への憧れが、2本しかないトム・ムーア監督の作品にどちらも、アカデミー長編アニメ映画賞ノミネートという高い評価を与えさせたのだろうう。彼の映画を観る時間、観客は、どこの国のなに人であったとしても、赤毛にそばかすのアイルランドの子供になるという疑似体験ができる。現地を旅したってせいぜい旅人気分しか味わえない。その文化の“中の人”だけが本来有している民族の目を持てる、というこのことは、すぐれて映画的な体験だ。まさに宮崎アニメがそうだったように。 であるのだから、03年に宮崎駿の『千と千尋の神隠し』がそうなったように、トム・ムーア監督作品もアカデミー賞受賞の栄誉に輝く日が、遠からず来るのではないかと感じる。■ 監督:トム・ムーア 出演:デヴィッド・ロウル、ブレンダン・グリーソン、リサ・ハニガン、ルーシー・オコンネル 脚本:ウィル・コリンズアートディレクター&プロダクションデザイン:エイドリアン・ミリガウ音楽:ブリュノ・クレ、KiLA 2014年/93分/アイルランド・ルクセンブルク・ベルギー・フランス・デンマーク合作/カラー/ビスタサイズ/DCP/5.1ch/原題:SONG OF THE SEA /日本語字幕:山内直子・高崎文子 ©Cartoon Saloon, Melusine Productions, The Big Farm, Superprod, Nørlum 提供:チャイルド・フィルム、ミラクルヴォイス、ミッドシップ配給:チャイルド・フィルム、ミラクルヴォイス宣伝:ミラクルヴォイス 後援:アイルランド大使館 2016年8月20日(土)、YEBISU GARDEN CINEMA他全国公開!http://songofthesea.jp/